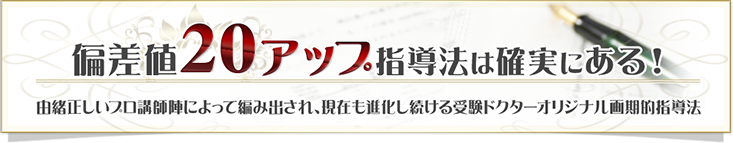こんにちは。
受験Dr.の吉野です。
「朝学習はいいとは聞くが、なかなか朝が起きられず継続しない」 そういったお悩みの声をよく聞きます。
今回は、朝学習を継続的に続けるコツおよび注意ポイントについてお答えしていきます。
① 朝学習のメリット
朝学習をやった方が良いと言われる理由は何でしょうか。以下のメリットがあります。
・集中力が上がる
脳は眠っている間に前日の記憶を整理するので、朝起きたときは脳がクリアな状態でいます。また、活動している人が少ない朝は、とても静かです。勉強に集中力できる環境が整っています。
・学習の習慣化がしやすい
朝は、登校までの限られた時間の中で洗顔、歯磨き、着替え、朝食とやるべきことが決まっています。その中に朝学習を組み込めば自然と朝のルーティーンが完成し、習慣化しやすいのです。またこの朝学習によって、時間制限の中で学習を完成させるという意識が付き、他の時間帯でも時間を気にして学習に取り組めるようになります。
・入試で実力を発揮できる
ほとんどの入試は午前中から始まります。そのため、朝から勉強する習慣がついていれば、朝からしっかり脳がはたらき、普段通りの実力を発揮しやすくなります。入試近くなってからでなく、早い段階から普段の生活の中に朝学習を取り入れる事をお勧めします。
➁ 朝学習で何をやるか
では、朝学習で何をやればいいのでしょうか?おすすめは「計算練習」です。
算数の力を上げる上で計算力の強化は必要不可欠です。この計算力は1日や2日ですぐに身につくものではなく、日ごろの練習が必要となります。また、計算練習は10分や15分ぐらいの短時間で終了させることができるので朝学習に最適です。
SAPIXの「基礎トレ」や四谷シリーズの「計算」や市販の「下剋上算数」などで時間制限を設けて実施してみてください。
【暗記は夜やる】
一方で、「漢字・語句の暗記」「理科や社会の知識の暗記」などの暗記は夜に行いましょう。脳は寝ている間に記憶を整理して定着させるはたらきをすると言われています。そこで夜に暗記して、覚えたかどうかを翌朝の朝学習で「暗記の確認」をすることをお勧めします。
③ 朝学習の注意点
せっかく朝学習を行うのであれば、以下の点に注意して実施してください。注意点を意識するだけで、学習効率が格段にあがります。
(1) ゴール(内容と時間)を具体化・数値化して設定する
「テキストの計算演習の1ページを10分で終わらせる」など、「何」を「何分」で終わらせるかを決めて下さい。「30分間でやれるところまでやる」というようなあいまいな計画は駄目です。
目標を設定することで、時間内にやらなければならないことが明確になり、集中力が増します。また、「いつもなら時間内に終わっていたのに今日は半分しかできなかった」など、自分の苦手単元の洗い出しやその日の集中力を確認するパラメータにもなります。
(2) 記録に残して反省会を実施する
やりっぱなしでは力が付きません。必ず「反省」して次につながる「改善策」を考えなければなりません。もちろんお子様に任せても構いませんが、できればおうちの方とお子様が一緒になって「反省」と「改善」を行ってください。その基準となるのが、日々の朝学習の記録です。
実施したテキストの上部に ①実施日 ②実施時間 ③正答率(点数) を記入してください。
1週間を目安に「反省」を行いましょう。「目標時間内に終わらない」などの時は、目標時間を長く設定しなおしたり、発展問題は飛ばしたりなどの「改善」を考えてください。
(3) 誰かといっしょにやる
ひとりでやると「やる気」が続かない場合があります。その時は、誰かといっしょに朝勉強してください。誰かといっしょに勉強すると、自分もやらなければという気持ちになります。
兄弟やおうちの方を誘って勉強してもいいです。また、友達と朝勉強の内容を報告しあうのもいいです。周りの人を巻き込むことで自分がさぼれない状況を作ってみてください。
(4) 睡眠時間をしっかりとる
睡眠時間を削って朝学習に取り組もうとする方もしばしばお見かけします。しかし、睡眠時間を削るのは絶対に避けてください。十分な睡眠時間を確保していないと、集中力が続かず、疲れが取れきれずに1日を無駄に過ごしてしまいます。最低でも9時間の睡眠時間を確保したいところです。そのためには、夜の早めの就寝を心掛けてください。
④ 朝学習の成功例
ここでは具体的な朝学習の成功例を見ていきます。それぞれ問題点がありましたが、上手く解決できていました。
【事例①】 朝が起きられない・・・楽しみとセットで
どうしても朝が起きられないお子様の相談を受けました。お話を聞いていると、原因は睡眠時間が足りないことと、お子様のモチベーションが上がらないことでした。そこでまず、就寝時間を午後10時にして、睡眠時間の確保をお願いしました。次に、お子様とお話をして、何をしているときが楽しいかを聞きました。ゲームをしているときが楽しいとのことで、保護者の方と相談して、朝学習ができた日は特別に午後に自由時間を設けてゲームをしていいというルールを作りました。翌日から、ゲームをしたいために朝起きてはりきって朝学習に取り組んでいたとの報告を受けました。
ここでは動機付けが大切です。無理やり強制させられてやるのでは長続きしません。何か楽しみとセットで朝学習を取り入れるのもひとつの方法です。
【事例➁】 朝学習は気分がのったときしかやらない・・・少しの時間から始める
毎日継続して朝学習ができず、気分がのるときだけ朝学習をするとのことでした。そんなお子様は、はじめは5分でいいので朝学習の時間を確保し、その後、ゆっくり時間をかけて学習時間を増やしていきましょう。いきなり大きな目標をたてても三日坊主では意味がありません。少しでもいいので継続することが大切です。
ここでは継続することが大切です。少しの時間から始めて継続して続けられるよう工夫をしましょう。また、「日記をつける」「実施内容をおうちの方に報告する」など、他の人から承認される、褒められる、なども継続するための要因になるでしょう。
【事例③】 睡眠時間が確保できない・・・塾から帰ったらすぐ寝る
朝学習を始めると、どうしても睡眠時間が削られるとのことでした。そこで、塾のある日などは、塾から帰ったらできるだけ早く寝て、その分早く起きて、朝時間を活用する勉強を提案しました。その結果、短時間で集中して課題がこなせるようになったとの報告がありました。このお子様の場合、夜10時には就寝して、朝7時に起床、30分の朝学習を行っているとのことでした。
ここでは睡眠時間の確保が大切です。睡眠時間を削ってまで学習することは集中力の低下を招き、結果として学習効率が悪くなります。短時間で集中して学習する、オン・オフの区別をつけて学習する、ダラダラ机に向かわないなど、学習の質を高めるようにしましょう。
今回はここまで。朝学習を有効に活用して朝の学習習慣を身につけましょう。
では、また次回でお会いしましょう。
受験Dr.吉野でした。