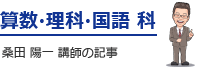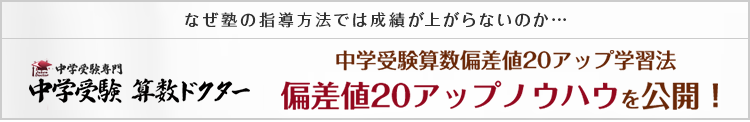みなさん、こんにちは。受験Dr.の桑田陽一です。
11月の講師ブログをお届けします。
今回は、場合の数の典型題から「ちょっと差がつく一工夫」を1つ紹介します。
問題
0,1,2,4,5,7のカードが1枚ずつあります。
この6枚のカードから3枚を並べてできる3けたの整数のうち、3の倍数は何個ありますか。
-----
「こんなの楽勝!」と思えた6年生は、とても頼もしいですね。確かに、場合の数の演習問題として何回も触れてきていることでしょう。
すぐ下に解答を書くので、解けそうだという人は答えを出してから読んでくださいね。
解答
3の倍数を作るためには、3枚の数の和が3の倍数であれば良い。
和が3の倍数になるような3枚の組み合わせは、
(0,1,2)、(0,1,5)、(0,2,4)、(0,2,7)、(0,4,5)、(0,5,7)、(1,4,7)の7通りある。
これらの組み合わせを並べ替えてできる整数は、
0をふくむ、(0,1,2)、(0,1,5)、(0,2,4)、(0,2,7)、(0,4,5)、(0,5,7)の6通りの組み合わせについては、それぞれ4個ずつ。
0をふくまない、(1,4,7)については、6個。
よって、6枚のカードを並べてできる3けたの3の倍数は、4×6+6×1=30通り。
-----
思った通り、楽勝でしたか?ミスすることなく、すべての場合を求められたでしょうか?
「ちゃんと解法は分かっていたけど、数え落としてしまった…」という人もいそうですね。
この問題を解くときに、最もミスをしやすく、また時間を食いやすいのは、和が3の倍数になる7通りの組み合わせを書き出すところです。
小さい数から順番に書き出していく作業の中で何通りかを飛ばしてしまったり…。
あるいは、7通りを書き出すことができたとしても、これですべてだという確信が持てずに時間を使ってしまったり…。
そんなミスや時間の消費を防ぐ、意外と知らない人が多い視点を紹介します。
それは、「カードを、3で割った余りで3グループに分類する」ということ。
これだけではピンと来る人は少ないと思いますので、以下に詳しく説明します!
「0,1,2,4,5,7」の6枚のカードを、3で割った余りに注目して分類すると以下のようになりますね。
余り0→0
余り1→1,4,7
余り2→2,5
さて、これらの6枚のカードから3枚取り出したときに和が3の倍数になるのは、大きく分けると以下の2通りの場合に限られます。
① 3つのグループから各1枚ずつ取り出したとき。
確かにこのとき、余りに注目すれば、0+1+2=3→3の倍数になりますね!
② 同じグループから3枚を取り出したとき。
仮に余り0のグループから3枚取り出せば、0+0+0=0。
余り1のグループからなら1+1+1=3、余り2のグループからなら2+2+2=6と、やはり3の倍数になるのは明らかです。
そして、これらの2つ以外の取り出し方では、3枚の和が3の倍数になることはありません。
この視点を持って、もう一度「0,1,2,4,5,7」から和が3の倍数になるように3枚取り出す組み合わせを考えてみましょう。
①の場合
余り0のグループは1枚、余り1のグループは3枚、余り2のグループは2枚。
ここから1枚ずつ取り出す場合の数は、1×3×2=6通り。
②の場合
3枚以上のカードがあるのは余り1のグループのみ。ここから「1,4,7」と取り出す1通りのみ。
よって、和が3の倍数になる組み合わせは「6+1=7通り」と自信を持って求められますね!
「この視点は初めて知った!」という受験生は、この機会に頭に入れておいてください!
「この考え方も知っていたよ!」という人、素晴らしいですね!
では、この視点をヒントに、以下の発展問題に取り組んでみましょう!
ノーヒントでは相当な難問ですが、今ならすんなり解けるかも?
チャレンジ問題
1,2,3,4,5,6,7を用いて5けたの数をつくります。ただし,同じ数字を何回用いてもかまいません。
12345 のように,となり合ったどの3つの位の数字の和も3の倍数となる数は何通りありますか。
(甲陽学院2024 2日目より)
-----
単に樹形図で整理しようとするのでは大変すぎ。まずは、「1,2,3,4,5,6,7」を3グループに分けるところから考えてみてください。
次回、解説編です。