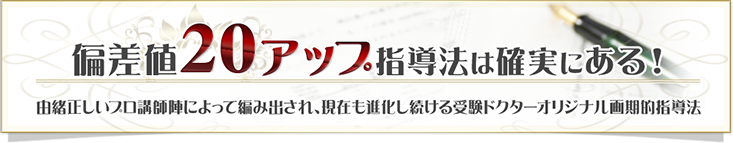皆さんこんにちは!
受験Dr.の清水栄太です。
緯度・経度は地理の“スタート地点”!
中学受験の社会科、とくに地理分野では「緯度」と「経度」の理解がとても大切です。
近年の入試でも出題される機会が増加しています。
でも、「緯度」と「経度」という言葉だけ聞くとちょっと難しそうに感じる方も多いですよね。
実はポイントをつかめば、読み解くのが簡単になるんです!
まず、緯度(いど)は「赤道からどれくらい北や南にあるか」を表す角度のこと。
北極が北緯90度、南極が南緯90度です。
そして経度(けいど)は「地球を東西に分ける角度」で、イギリス・ロンドンのグリニッジ天文台を0度(これを本初子午線といいます)としています。
地球は東経180度と西経180度で一周するんですね。
日本の“住所”を確認してみよう!
日本が地球のどのあたりにあるのかを、緯度・経度で見てみましょう。
日本の緯度は、北緯約20度~46度の間。
一番南は東京都の沖ノ鳥島(北緯約20度25分)、一番北は北海道の択捉島(北緯約45度33分)です。
この広い緯度の範囲が、日本に「四季」がある理由のひとつなんです。
一方、経度は東経約123度~154度。
西の端は沖縄県の与那国島(東経122度56分)、東の端は東京都の南鳥島(東経153度59分)です。
この差だけで本来は2時間ほどの時差ができますが、実際には全国が東経135度の標準時を使っています。
したがって、日本のおおよその範囲は
南北に約25度、東西に約30度広がっている点をおさえましょう!
ここがポイント!日本を通る“有名な緯度経度線”
中学受験では、特定の緯度線がどこを通っているかを問う問題がよく出ます。
とくに以下の3本はチェック必須!
北緯35度線:日本のまんなかを通る有名な緯度線。
房総半島や伊豆半島の北部、大津市、京都市、島根県の江の川河口付近など
地理的要素と関わりの深い地点を通過しています。
北緯40度線:秋田県男鹿半島の近く、八郎潟干拓地を通ります。
東経140度線と八郎潟付近で交わるという点が重要な部分ですね!
北緯45度線:北海道の稚内市の少し南。
択捉島がこの北緯45度線上にあります。
経度では「明石」が基本!
経度でまず覚えておきたいのは、東経135度線。
兵庫県の明石市を通り、「日本の標準時子午線」として知られています。
この線は京都府京丹後市、兵庫県豊岡市、和歌山県南部なども通過します。
「明石=東経135度=日本標準時」――この3点セットで覚えるのがコツです!
そして、東経135度のみではなく、東経140度までおさえることが重要なポイント。
東経140度の経線は、猪苗代湖の西部や埼玉県と東京都の東部を通過し、
房総半島で北緯35度線と交わります。
通過する位置をおさえておきましょう!
緯度と経度は、地理のあらゆる分野につながる“土台”です。
日本の位置を緯度や経度としておさえることで、気候・時差・産業など多くの問題につながります。
地図帳を開いて、実際に線を引きながら確認してみましょう。
きっとの日本が、もっと身近に感じられるはずです。
今回はここまで。
それではまた次回お会いしましょう!
応援しています!