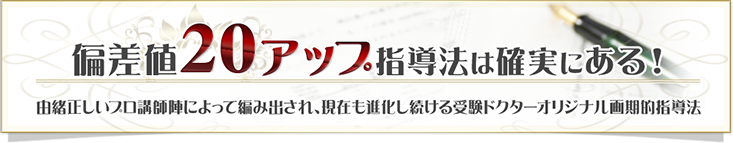皆さま、こんにちは!
「そもそも偏差値ってなに?」ということを考えていくシリーズ、今回はその第6回です。
偏差値の創案者として知られる桑田昭三先生のご意見も引用しつつ、偏差値の扱い方を考えています。
第3回で、現代の中学受験でどう偏差値をとらえるべきかについて、以下の4点をポイントに挙げました。
①そもそも偏差値はぶれるもので、最大で偏差値6くらいの上下は自然に起こる
②偏差値同士の比較には注意が必要で、特に同内容の試験でなければ推移を追うことにあまり意味はない
③偏差値を利用して受験の合否を判断する場合、向いている試験と向いていない試験が存在する
④偏差値はひとつの指標であって、試験内容、順位、平均点など、他の要素と総合的に考える必要がある
この4点は創案者の桑田先生のお考えをもとに、私の知識や経験も加えて解釈したものです。
そこまで詳しいことは必要ないという方は、最低限、この4点を覚えておいて頂ければ十分です。
今回は、この4つのポイントのうち、③についてより詳しく説明していきます。
なお、今回のブログでも以下の2つの参考資料を用いています。
1つは、1976年に徳間書店から発刊された『創案者が初公開する進学必勝法 偏差値の秘密』です。
以下、『偏差値の秘密』とします。
資料の2つ目は、インターネット上で公開されているインタビュー記事です。
2010年にJALTというNPO団体が桑田先生に行ったインタビューをもとにして書かれています。
現在も公開されていますので、興味のある方は以下のURLをご参照ください。
https://teval.jalt.org/test/PDF/Kuwata-j.pdf
以下、『桑田昭三氏へのインタービュー』とします。
模試によって合格判定が得意なゾーンがある
後期の6年生の模試は、多くの場合、偏差値とあわせて学校ごとの合格判定を知ることができます。
合格判定は、当然偏差値をベースに出しているのですが、この数字はどこまで信じていいものでしょうか?
基本的には、志望校選択や合格判定に関して、それぞれの模試の判定をベースに考えるのが基本です。
同じ試験内容で、たくさんの受験生と競っての結果ですから、自分の立ち位置という意味で間違いはないです。
合格判定は、以前に何度か書いたように、合格可能性が50%であれば、十分勝負になると考えて大丈夫です。
ただし、ひとつ気をつけた方が良いのは、模試によって判定の精度が高いゾーンが異なるということです。
たとえば、サピックスオープンのような問題の難易度がわりと高めのものは、上位校の判定精度が高いです。
一方、首都圏模試のような比較的問題の難易度が低い模試の場合は、中堅校の判定精度が高いです。
これは、どれが良い悪いというわけではなく、どのあたりに焦点を絞った模試なのかということです。
それぞれの模試に、判定が得意なゾーンと不得意なゾーンがあると考えてください。
お子さんの志望校の判定に強い模試はどれなのかということを考えて、模試を変えてみることも大切です。
学校によって出題形式・傾向は異なる
それに加えて、模試と志望校の出題形式・傾向がどの程度一致しているのかも重要です。
入試本番の出題形式・傾向によっては、模試の偏差値や合格判定だけでは何とも言えないこともあります。
中学入試の場合、学校ごとに出題の特色が異なることが多いからです。
ひとつひとつの学校や科目を挙げているときりがないので、各学校で特色が出やすい国語を例に説明します。
一般的な模試の国語では、漢字、語句知識、論説文、物語文とバランスよく全分野から出題されます。
読解問題の解答形式も、多くが選択肢問題で、記述は1問ずつくらい、他に抜き出しや空所補充などが少々。
多くの模試がこのような感じです。
しかし、実際の入試問題では、必ずしもこの通りの出題というわけではありません。
例えば、開成、麻布、桜蔭、鴎友、学習院女子などの学校は、ほぼすべての解答が記述形式です。
しかも、どのくらいの文字数の記述を求めるかは、これらの学校でも異なります。
また、素材文に関しては、麻布、駒場東邦、学習院女子、城北などの学校は物語文1題の出題になります。
逆に、明大明治は論説文1題の出題しかなく、こちらはレアケースです。
武蔵のように、素材文のジャンルはランダムで1題という学校もあれば、女子学院は随筆文が2題出ます。
詩・短歌・俳句などの韻文の出題があるかどうかも、学校によって異なります。
漢字や語句知識も、少ししか出題しない学校も多くあります。
一方で、攻玉社のように毎年難しい問題を出題することで有名な学校もあります。
以上は一例ですが、国語の入試問題の形式・傾向が、学校ごとに大きく異なるのがわかると思います。
こうなってくると、模試の国語の偏差値だけでは、その学校の問題に通用するかは明確にはわかりません。
もちろん、模試の国語の偏差値が常に高いのであれば、国語の総合力が高いのは間違いないです。
しかし、例えば記述形式の解答だらけの学校を受けるのであれば、記述力は別に確認した方が良いです。
どの程度の記述力があるかは、必ずしも偏差値からだけでわかるものではありません。
こういった一般的な模試では測れない問題が、他の科目でも見られるのが中学入試の大きな特徴です。
高校入試では、公立高校の問題であれば、すべての学校がそれぞれの県ごとに共通問題で行われます。
模試もそれぞれの県の出題に沿ったものになるため、公立型の模試の判定の精度は非常に高いです。
一方、私立高校の問題になると、学校によって異なってくるものもあります。
そのため私立型の模試や、上位生や難関高校受験者を対象にした高い難易度の模試も存在します。
実際に、創案者の桑田先生も著書の中で次のように書かれています。
私立高校入試は大別すると、(1)公立高校の入試に準拠した形で行われる場合、(2)その
私立高校独自の、個性的な試験で行われる場合、の二つに分けられます。
(1)の場合は、一般に使われている偏差値から合否をほぼ正確に予測できます。しかし(2)のような高校では、個性的な、あるいは癖のある試験をするものですから、一般に行われている
テストから偏差値を出し、正確に合否を予測するのはむずかしいこともあります。しかしまった
く予測できないというのではなく、誤差の幅が大きくなるという意味です。
形式・水準・傾向・分野・領域などが違うと、ふだん行っているテストでよい点がとれても、
正確さに欠けるデータとなってしまいます。(2)に該当する高校を受ける場合は、出題される
傾向や形式に沿った測定方法で偏差値を出せば、誤差の幅も少なく、より正確なものとなるでしょ
う。
このように、一概には、私立高校入試の合否を偏差値で正確に予測できるとはいいがたいもの
です。まず、学校によって違うことを念頭においてください。
(『偏差値の秘密』189〜190ページ)
以上の内容は、1970年前後の高校入試を背景にしたものですが、今でも大きくは変わらないと思います。
また、中学入試における模試と、それぞれの中学校の入試問題の関係にもあてはまる部分が多いです。
桑田先生が書かれているように、どうしても「誤差の幅が大きくなる」傾向が中学入試にはあります。
では、どうしたらより誤差の少ないデータが手に入るのか?
まず、有名中学については、大手の進学塾が学校別の模試というのを9月から11月を中心に行います。
学校別の模試がある場合は、やはりこの模試での結果をより重視して考えるのが基本です。
それぞれの学校の出題形式・傾向にあわせた問題になるので、どの程度の対応力があるかがわかります。
さらに大きいのが、模試の受験者の多くが、実際にその学校の受験を考えている受験生になることです。
やはり、実際の入試本番でもライバルになる相手と、同じテストで競ったデータは信頼性が高いです。
学校別の模試がない場合はどうしたらよいかですが、これはやはり過去問を解いて相性を見るのが基本です。
その学校の出題形式・傾向にうまく対応できているかは、実際に過去問をやってみて判断しましょう。
また、誤差が大きいとはいっても、普段の模試の偏差値・判定が役に立たないという意味ではありません。
ある程度の幅やブレを念頭において、偏差値や判定を見れば大丈夫です。
偏差値5くらいはブレるということと、合格判定が50%前後の学校は十分合格できるという方針でOKです。
学校別模試の注意点
最後に、学校別の模試の結果の受け止め方について、ひとつ注意点を書いておきます。
学校別の模試を受けた生徒に感想を聞くと、「過去問より難しかった」という反応であることが多いです。
この感覚は間違っておらず、実際に私が解いてみても、「実際はこんなに難しくはない」と感じることが多いです。
ですから、極端に低い点数が出ても焦らずに、平均点や偏差値、受験生の中での順位を冷静に見ましょう。
では、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?
学校別の模試というのは、テスト作成者がそれぞれの学校ごとの特色をうまく取り入れようと苦心して作ります。
これは大変な作業で、形式や雰囲気をあわせるだけでも、作問にかなりの工夫と労力が必要です。
しかし、その学校の特色をあまりに出そうとすると、どうしても全体的に難しくなりすぎてしまう傾向があります。
それぞれの学校が過去に出題した特徴的な問題というのは、そもそも難しい問題であることが多いです。
そのため、そういった問題の類題を多く集めると、必然的にテスト全体の難易度は上がってしまうのです。
ですから、合格ラインと言われるような点数より低い点数が出ても、あまり気にすることはないのです。
また、全体的に平均点が低くなりすぎたケースの場合は、合格判定もあまり当てにならなくなってきます。
あまりに平均点が低くなりすぎると、受験者に有意な差がつかなくなるからです。
全員が0点という極端なケースを考えてみれば、そのテストでは何もわからない、ということがよくわかります。
実際に私が数年前に指導していたお子さんで、同様のケースがありました。
そのお子さんは、それまでのすべての模試で、第一志望校の合格判定が60%〜80%と出ていました。
私の指導実感からも、まず間違いなく合格すると思っていました。
ところが、そのお子さんが学校別の模試を受けたところ、なんと合格判定が20%と出てしまったのです。
お子さん自身はわりとけろっとしていたのですが、お母様は青い顔をされていたのをよく覚えています。
私はその判定を見た瞬間に、そんなはずは絶対にないと思いました。
詳しく成績表をチェックし、問題も実際に解いてみると、あまりに難しく平均点も極端に低いことがわかりました。
先ほども書いたように、残念ながらこのテストでは何もわからないという、のが私の判断でした。
以上のことをお母様に説明し、「まったく心配ないです。必ず合格します。」と伝えて、安心して頂きました。
結果的に、そのお子さんは第一志望のその学校に無事に合格しました。
これは一例でしかないですが、こういうこともあると知っておくのが良いと思います。
毎回書いていることですが、一回の模試の結果だけでは何もわかりません。
低い数字が出ると不安になるのは仕方がないですが、それに振り回されるのは避けましょう。
冷静にそれまでの模試の結果や、過去問の点数などを総合的に考えて判断することが大切です。
次回はポイント④について、詳しく解説します。
では、また次回お会いしましょう!