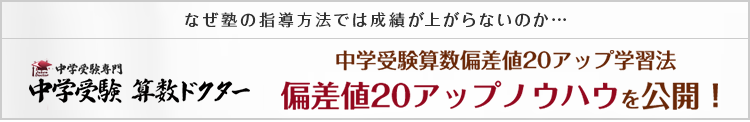みなさん、こんにちは。
受験Dr.算数科の江田です。
今回は「円に引く補助線」について、
その中でも角度を求める問題を取り上げます。
さっそく例題です。
まずは基本問題から。
【例題1】
下の図のように、点Оを中心とする円があります。
図の角アは何度ですか。
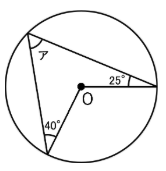
さて、ここで意識してほしいこと。
それが今回のブログのテーマ、「円に引く補助線」についてです。
「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」
これが今回伝えたいこと。
これを合言葉に問題に取り組みましょう!
そう、下のように中心Оから点Pを結ぶ補助線を引くわけです。
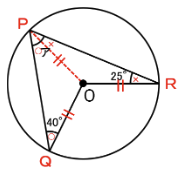
すると
OP=OQ=OR(すべて半径)となるので、
図のように◯どうし、✕どうしがそれぞれ同じ角度になります。
よって、角アは
40+25=65(度)
と求まります。
それでは次の例題です。
次は標準問題。
【例題2】
下のように、
点О、点Pを中心とする同じ大きさの円の円周が
それぞれの中心を通るように重なっています。
図の角ア、角イの大きさはそれぞれ何度ですか。
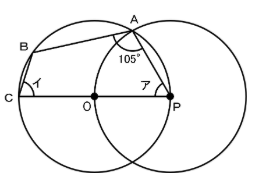
ここでも
「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」
を合言葉に取り組んでみましょう。
下の図のように補助線を引きます。
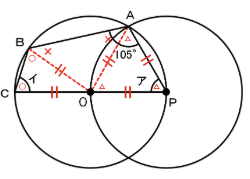
すると
OP=OA=OB=OC=PA(すべて半径)となり、
図のように◯どうし、✕どうし、△どうしがそれぞれ同じ角度とわかります。
そう、つまり三角形OAPは正三角形だったんですね!
よって、角アは
180÷3=60(度)
と求まります。
そして、✕は
105-60=45(度)、
角AOBは
180-45×2=90(度)、
角BOCは
180-(60+90)=30(度)
と求まります。
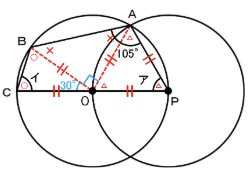
よって、角イは
(180-30)÷2=75(度)
となります。
ちなみに、
「四角形ABCPの内角の和(360度)が〇✕△2つずつの合計である」
ことに気付くことができれば、
〇✕△1つずつの合計が
360÷2=180(度)
とわかるので、角イは
180-105=75(度)
と簡単に求めることもできます。
さあ、次が最後の例題です。
最後は応用問題。
【例題3】
下の図において、
点Оは円の中心で、OA=DEとなっています。
このとき、角アは何度ですか。
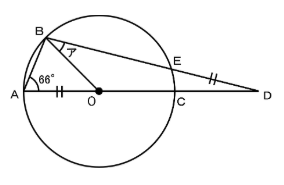
さあ!
ここでも
「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」
が合言葉!
どこに補助線を引けばよいのか、わかりますか?
“半径”を引けそうなところ・・・
正解は・・・
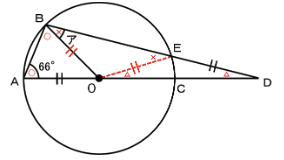
上の図のように点Оと点Eを結ぶのです。
すると
OA=OB=OE=DE
となるため、
◯どうし、✕どうし、△どうしがそれぞれ同じ角度とわかりますね。
ここで
三角形ODEにおいて「外角の定理」を利用すると
✕は△2つぶん
とわかり、三角形OBDにおいて「外角の定理」を利用すると
角AOBは△3つぶん
とわかるので、下の図のように整理できます。
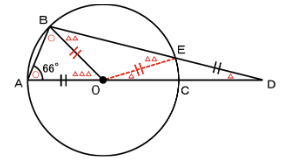
このことから、△1つは
(180-66×2)÷3=16(度)
と求まり、角アは
16×2=32(度)
と求められます。
いかがでしたか。
基本問題から応用問題まで、
すべて“半径”を引いて考えることがキーポイントとなっていたことが
わかっていただけたかと思います。
是非お子様に
「円に引く補助線といえば“半径”を真っ先に疑え!」
という合言葉を確認してあげてください。
きっと、問題を解く手がかりになってくれることでしょう。
今回はここまで。
また次回のブログでお会いしましょう!