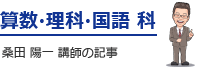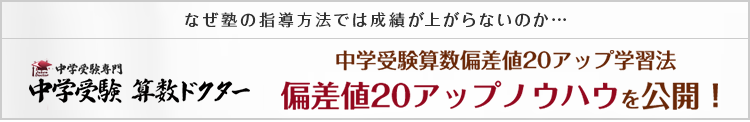みなさん、こんにちは。受験Dr.の桑田陽一です。
10月の講師ブログをお届けします。
今回は、前回紹介した京都大学入試の解決編です。
問題
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができる整数Nのうち、最も小さいものを求めなさい。
(2025京都大学 理系 大問2 改)
問題の表現は大幅に改めていますが、数学的な内容はそのまま。
ノーヒントではさすがに難しいので、前回の記事では小問を付け加え、ステップに分けて考えました。
その結果、
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができるとき、「BもCも3の倍数である」
ということを確認したところまでが、前回のお話。
今回は、これを用いて、元の問題の答えを求めます。
前回は少し込み入ったことを考えましたが、BもCも3の倍数であると分かれば、この後のステップは中学受験生にも無理なく理解できるはず。
では、見ていきましょう。
-----
(3)
以下の文の空欄に当てはまる、最も大きい整数を答えなさい。
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができるとき、
(2)より、B×B×B×B×B×Bは必ず( ① )の倍数であり、C×C×C×Cは必ず( ② )の倍数です。
-----
前回の(2)で、BもCも3の倍数であることが分かっています。
B×B×B×B×B×Bは、3の倍数を6個かけ合わせた数なので、3×3×3×3×3×3=729の倍数です。
同じように、C×C×C×Cは、3の倍数を4個かけ合わせた数なので、3×3×3×3=81の倍数です。
-----
(4)
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができる整数Nのうち、最も小さいものを求めなさい。
-----
いよいよ、京都大学で出題された元の問題の答えが求まります!
(3)で、B×B×B×B×B×Bは729の倍数であり、C×C×C×Cは81の倍数であると分かりました。
問題で与えられている式、N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×Cは、729の倍数と81の倍数の和が、9×A×Aという形の数になっているということですね。
このような整数のうち最も小さいものを求めるので、まずはB×B×B×B×B×BやC×C×C×Cとしてあり得る値を、小さい方から考えてみましょう。
B×B×B×B×B×Bの最も小さな値はもちろん729、C×C×C×Cの最も小さな値は81です。しかし、これらの和である729+81=810は、9×A×Aの形で表すことはできません。
810=9×A×Aだとすると、A×A=810÷9=90となりますが、90は平方数ではありませんね。
では、B×B×B×B×B×Bとして考えられる、小さい方から2番目の値は何でしょうか。729の倍数だから729×2=1458のような気もしますが、実はそうではありません。
B自体が3の倍数でしたから、3×3×3×3×3×3の次は、6×6×6×6×6×6、その次は9×9×9×9×9×9…と続きます。
同じように、Cも3の倍数ですから、3×3×3×3の後は、6×6×6×6、9×9×9×9…と続きます。
値を計算してみると、
B×B×B×B×B×Bは、729、46656、531441…と急激に大きくなります。
C×C×C×Cは、81、1296、6561…という感じで、少しゆるやかな増え方。
そこで、B×B×B×B×B×Bの方を729に固定して、C×C×C×Cの値を順に試していくと…
729+81=810 →×
729+1296=2025=9×15×15 →○
と、条件に当てはまる整数が意外と早く見つかりました!
すなわち、元の問題で問われていた「0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×Cと表すことができる整数Nのうち、最も小さいもの」は、2025です!
ちなみに、このときに使う整数A、B、Cは、順に15、3、6であることも分かりました。
2025年度の入試で出題された、答えが2025になる難問。本番で解けた受験生は気持ちよかったでしょうね!
2026年度入試を目指す中学受験生にとっては、2026という数の性質が気になるところですが、2025と違って約数の個数も少なく、問題はやや作りにくそうな数です。
良い問題が思いついたら、改めて紹介しますね。
今回はここまで。