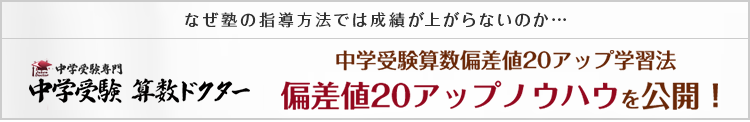みなさん、こんにちは。受験Dr.の亀井章三です。
今回もマルイチ算についてです。
前回は、マルイチ算という方程式を解くための方法について説明しました。
今回は、マルイチ算に持ち込むための前提である「式を作る」方法について
例を交えながら説明していきます。
問題例 開成中学 2025年
ショウヘイ君はいくらかのお金を所持しています。まず、所持金の19より20円安い
商品Aを買いました。次に、残金の17より40円安い商品Bを買いました。続けて、
このときの残金の15より10円安い商品Cを買ったところ、最後に残ったお金は
はじめの所持金の4割より480円多かったそうです。
商品Aの値段はいくらでしたか。
①まず、余計な文字は消して、必要な文のみ一つずつ並べます。
条件1 所持金の19より20円安い商品Aを買いました。
条件2 次に、残金の17より40円安い商品Bを買いました。
条件3 続けて、このときの残金の15より10円安い商品Cを買った
条件4 最後に残ったお金ははじめの所持金の4割より480円多かった
設問 商品Aの値段はいくらでしたか。
②さらに、割合に関する部分のみ取り出します。
所持金の19、残金の17、このときの残金の15、はじめの所持金の4割
数値の流れとしては、所持金→残金→このときの残金 となりますので、
一番上位にある「所持金」をマルイチで表すことにします。
所持金=①とすると、表しやすいですが分数主体の計算となり少し面倒です。
そこで、出てきた割合の分母の最小公倍数を使います。そうすると、分数が
少なくなり計算も楽になります。
4割=25なので、9と7と5の最小公倍数315を所持金とします(315)
③所持金の315を用いて、全ての条件を式にします。
残金やこのときの残金は、そのまま文字で表します。
また、多い=「+」、安い=「-」になります。
(A+B)×C=A×C+B×Cの関係を使います。
条件1 所持金の19より20円安い商品Aを買いました。
→ 商品A=315×19-20=35-20
⇒ 残金=315-(35-20)=280+20
条件2 次に、残金の17より40円安い商品Bを買いました。
→ 商品B=残金×17-40=(280+20)×17-40=40-2607
⇒このときの残金=(280+20)-(40-2607 )=240+4007
条件3 続けて、このときの残金の15より10円安い商品Cを買った
→ 商品C=このときの残金×15-10=(240+4007 )×15-10=48+107
⇒ 最後に残ったお金=(240+4007 )-(48+107)=192+3907
条件4 最後に残ったお金ははじめの所持金の4割より480円多かった
→ 最後に残ったお金=所持金×0.4+480
→ (192+3907)=315×0.4+480
→ 192+3907=126+480 ここで移項を使い、1を求めます。
→ 192-126=480-3907
→ 66=29707
⇒ 1=29707÷66=457
設問 商品Aの値段はいくらでしたか。
商品A=35-20 に、1=457を代入します。
35×457-20=225-20=205
よって、商品Aは205円です。
ほぼ全ての文章題は、文字式を用いることで解くことができます。文章上の表現
を正しくとらえ、+、-、×、÷のどの計算にあたるかを考えます。そして、割合を
マルイチで表現することで式を立てるという流れを常に意識しましょう。