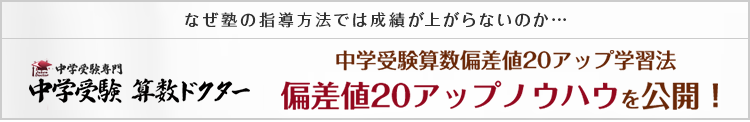みなさん、こんにちは。
受験Dr.算数科の江田です。
今回は「〇でわると△あまる整数」について、
その中でも最も基本となる問題を取り上げます。
たとえば、
「8でわると3あまる整数」
を小さい順に5つ書き出してみてください。
(ぜひお子様にも聞いてみてください。)
正解は下のようになります。
3,11,19,27,35
いかがでしょう。
一番小さい整数が3ではなく11になってしまっているお子様はいませんでしたか?
これ、結構多く目にする間違いです。
8でわると3あまる最も小さい整数は
8でわったときの「商が0」であまりが3のときなんですね。
つまり、
□÷8=0あまり3
となる場合の□にあてはまる整数です。
よって、
□=8×0+3=3
が最も小さい整数とわかります。
ということで、あらためて書き出すと
3,11,19,27,35
となっており、これは
「はじめの数が3で、8ずつ増えていく等差数列」
であることがわかります。
そう、つまり
「〇でわると△あまる整数」
というのは、
「はじめの数が△で、〇ずつ増えていく等差数列」
となっているんですね!
よって、たとえば
「8でわると3あまる整数のうち、小さい方から100番目の数は?」
という問いに対する答えは、
3+8×(100-1)=795
と求めることができます。
さて、ここで今の問題を次のように考えてみます。
「8でわり切れる整数」だったら、それすなわち「8の倍数」ですよね。
よって、「8でわると3あまる整数」は
「8の倍数よりも3大きい数」
と考えることができます。
つまり、
「8×□+3」
という式で表せる整数となります。
(〇÷8=□あまり3 → 〇=8×□+3 と説明することもできます。)
この式
「8×□+3」
の□にあてはまる数のうち、最も小さい数は?
そう!
1ではなく0ですね。
よって、8でわると3あまる最も小さい整数は
8×0+3=3
と求められますし、
この式の形で考えると、
先ほどの「小さい方から100番目の数」は
□に100ではなく99を入れたときの
8×99+3=795
とわかります。
いかがでしょう。
「〇でわると△あまる整数」
を
等差数列としてとらえる
〇の倍数よりも△大きい数としてとらえる
という2つのアプローチ法を紹介しました。
どちらも汎用性・重要度の高いとらえ方ですので、
ぜひお子様と一緒に確認してもらえると幸いです。
今回はここまで。
また次回のブログでお会いしましょう!