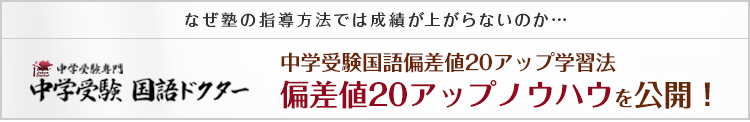こんにちは、太田 陽光です。
今回は、記述で何を書いたら良いか分からない人に、何を書けば良いかを教えます。
実は、記述で何を書けばよいのかが書いてある場所があるのです。
それは問いです。
問いには記述を書く際の条件やヒントがあるのです。
例えば、問いかけの言葉。
問いかけの言葉とは、「ど」か「な」で始まる質問の言葉のことです。
具体的には、「どうして」、「どういうこと」、「なぜ」、「何」などです。
この問いかけの言葉によって、記述の最後が何で終わるかが分かりますね。
「どうして」「なぜ」であれば「から。」
「どういうこと」であれば「こと。」
「何」であれば「名詞。」となります。
しかし、それだけではありません。
「どうして」「なぜ」であれば、理由を書く問いであることも、
「どういうこと」「どのようなこと」であれば言い換えを書く問いであることも、分かるのです。
論説文の問題では、問題の種類にかかわらず、理由と言い換えが問のほとんどを占めます。
理由と言い換えのどちらを書くのかの判別ができるだけでも、何を書いたら良いのかの方向性が見えてくるものです。
つまり、問いに書かれていることを、表面的に読むのではなく、検討しながら読むことが大切なのです。
実際の入試問題を見てみましょう。
【吉祥女子中学2024年第1回大問1】
問12 筆者は本文で、現在の日本のどのような問題点を指摘していますか。また、その問題点に対する筆者の解決策はどのようなものだと考えられますか。本文全体をふまえて80字以上90字以内で説明しなさい。
まず、問いかけの言葉は「どのような問題点」と「どのようなものだ」の2つあるので、2点答える必要があると分かります。
次に、1つ目の問いかけの言葉に注目すると、「問題点」とあるので、答えに「問題点」を使うことが分かり、そして、問題を書くのだと分かります。
さらに、「現在の日本」とあるので、現在のことや日本のことについて書いているところが答えに使えると分かります。
続いて、2つ目の問いかけの言葉に注目すると、どのようなものと書いているので、「もの」などの名詞を使うことが分かります。
さらに、「解決策」とあるので、解決策を書くことが分かります。
そして、「考えられます」とあるので、本文にはっきりと書いたところはなく、自分で考えて書くことが分かります。
ただし、自分で考えて書くと言っても、自分でつくり出す必要がなく、ほとんどの問いは本文に書かれた文言を反対にしたり、加工したりすることで答えを作れます。
本文は以下のようになっています。
住形態も生活様式も変化した現代人は…
他人と話をせず、笑顔を見せず、視線を向けようともしなくなったいま、つまり、まわりとのコミュニケーションが途絶えたいまになって、その重要性が叫ばれている。コミュニケーションを積んでこなかった現代人は、話し方教室だの自己啓発セミナーだのに通う。かつてはだれもがいつのまにか、したがってさほど苦痛もなく身につけたコミュニケーションのスキルをいまやお金を出して、苦労して習う時代なのだ。
…必要も機会もなくなったら、人は物を覚えない。
では、模範解答を見てみましょう。
住形態や生活様式の変化によってコミュニケーション能力が低下したという問題点を指摘している。その解決方法は、各自が対面でやり取りをする機会を増やして訓練を積んでいくことだと考えられる。
問いの「現在」と同じ意味の言葉のところが解答になっていることが分かります。
また、「解決策」に関しては、現在行われていないことが書かれたところを反対にしたものが解答になっていることが分かります。
「問題点」・「解決策」「もの」ではないが「こと」という名詞も解答に使われていることが分かります。
いかがでしたか。
もちろん、本文のどこにどのようなことが書かれているかを読み取る力は必要ですが、
記述で何を書いたら良いかわからない人には、問いに書くべきことが書いてあることが分かってもらえたかと思います。
まずは問いの条件やヒントを検討しながら読んでみましょう。