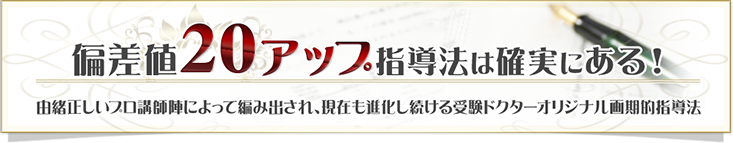こんにちは。
受験Dr.の吉野です。
6年生の11月は、最終的な志望校を決定する時期です。
「今まで目標にしていた第一志望校をかえた方がいいのか?」 「併願校はどこがいいのか?」そういったお悩みの声をよく聞きます。
今回は、最終志望校の決定の際に注意すべきポイントについてお答えしていきます。
① 志望校を考える4つの要素
志望校を決める際の要素は様々ありますが、私が特に重要と思う4つの要素について説明します。
(1) 進学実績
一番重要な要素だと思います。卒業生が実際にどの大学に合格しているかを確認しましょう。お子様が希望する大学や学部に進学実績があれば、理想的な志望校と言えます。また、中学入試時点での偏差値は比較的高いとは言えない場合でも、有名大学への進学実績が安定している学校は魅力的な学校と言えます。さらに、現役合格率(浪人せず大学に合格した割合)にも注目しましょう。現役合格率が高い学校の方が、お子様にとっても負担が軽くなるはずです。
(2) 通学時間
意外かもしれませんが、通学時間を気にしてください。これから6年間通う学校です。移動時間が長いとそれだけで疲れてしまい、授業に集中できなくなったり、学校に行きたくなくなったりします。また、朝の保護者様のお弁当作りの時間も通学時間によって影響を受けます。さらに、電車の通勤ラッシュも考慮してください。座っていけるなどのメリットがあれば、通学も苦にならないかもしれません。いずれにしても、通学経路を調べ、朝の通学をシミュレーションし、無理なく通えるか確認しましょう。
(3) 校風や教育方針
自主性を重んじる自由な校風の学校や、規則やルールに厳しい学校など、各学校の校風をしっかり確認しておきましょう。また、ネイティブ教員との対話など英語教育に力をいれていたり、理科実験など理数教育に力をいれていたりと、各学校の教育方針も重要になります。お子様の性格や将来の夢を考慮して選びましょう。
(4) 偏差値
お子様の偏差値を基準に学校の偏差値も確認しましょう。ただし、お子様の偏差値が基準を超えているから志望校にするなどといった、偏差値だけで志望校を決めるのは駄目です。上記の(1)~(3)の条件がお子様に合っていることが前提となり、偏差値はあくまでも参考として活用してください。
また、中学受験で成功して、ハイレベルな第一志望に合格したとしても、周りのお子様との競争についていけず、中学校からの勉強が上手く行かなくなるケースも少なくはありません。逆に、偏差値的にワンランク下でも、お子様にとってはマイペースに勉強ができ、入学後の結果を見ると、そちらの方が良かったというケースも珍しくありません。「鶏口となるも牛後となるなかれ」の故事成語のように、大きな集団の末端にいるより、小さな集団のトップになる方がいい場合もあります。
➁ 志望校決定の際の失敗例
ここでは、11月の志望校最終決定の際に起きた具体的失敗例について解説します。
(1) 偏差値だけで志望校を選んでしまった
偏差値が高いから良い学校だろうという理由だけで志望校に選んでしまいました。見事合格して実際に通うようになると、課題の多さについていけず学習意欲が低下してしまいました。
事前に教育方針を調べていれば、防げた状況だといえます。偏差値が高い中学に入学するのも魅力的ですが、お子様の人生にとって中学受験はひとつの通過点です。6年間の学校生活がつらくならないよう、通学時間・校風・教育方針など多角的な視点から志望校を検討しましょう。
(2) 本人に相談せずに志望校を決めてしまった
志望校選びで小学生のお子様に一任することが難しかったため、お子様の意向を無視して「ここに行きなさい」と保護者様が決めてしまいました。
志望校決定の最終的なカギとなるのは、お子様の意思です。実際に学校に通うのも、合格に向けて勉強をするのも、お子様本人です。お子様が本気で「行きたい」と思う志望校を持つことは、中学受験の成功にとって大きな強みであり、必須条件とも言えます。ご家族でよく話し合うことが大切です。
(3) 「○○中学以外に行くのなら、中学受験した意味がない」と激励してしまった
親としてはつい熱が入り「絶対にこの学校に行ってほしい」という気持ちから出てしまう言葉です。しかし、上記のような言葉は言ってはいけません。まず、1月の直前で志望校が変更になる可能性もあります。変更した場合、お子様の頑張ってきたモチベーションが一気に崩れ、取り返しのつかないケースが毎年多々あります。また、残念ながら志望校に通らなかった場合、自分は親の期待に応えられなかったというトラウマを感じてしまいます。何も良いことのない言葉ですので、ご注意ください。
③ 11月に志望校変更はした方がいいのか?
最終志望校決定の11月において、学力面での不安から志望校を下げるべきか考えている状況です。
模試の判定結果があまりにも低い場合を除いて、変更を検討する必要はないと考えます。志望校を変更することはお子様の自信を失わせ、モチベーションを低下させる可能性があります。変更する場合は、お子様の気持ちに配慮し、しっかり説得できる材料を用意しましょう。
また、志望校の変更はしないものの、併願校の見直しはしっかりと行うべきです。
④ 併願校の決め方
以下の3種類に併願校を分類します。「通いたい」と思う学校をそれぞれのグループから何校か選んでおいてください。
・押さえ校・・・偏差値が5ポイント以上低いレベルの学校。確実に合格できる学校。
・志望校・・・偏差値と同等レベルの実力相応の学校。合否判定テストで50~80%の学校。
・チャレンジ校・・・生徒様の偏差値より5ポイント以上高いレベルの学校。合否判定テストで30~50%の間の学校。
(1) ケース1:第一志望校が「チャレンジ校」の場合
模試の判定結果が悪くても、直前の追い込みによっては合格の可能性もあるので、あきらめずに受験しましょう。ただし、志望校、押さえ校を複数校選んでおくことが必須となります。首都圏の方は、埼玉県や千葉県の1月受験校でまず押さえ校を受験し、一足先に合格を掴み取れれば安心です。
(2) ケース2:第一志望校が「志望校」の場合
第一志望校に全力で挑んでください。ただし、受験では何が起こるか分かりません。押さえ校も何校か選んでおきましょう。また、第一志望校と似ていて、行きたいと思う学校を第二志望校として受験するのもお勧めです。複数のレベルの行きたい学校を受験して、万が一第一志望の学校に合格できなくても、進学できる学校を確保しましょう。
⑤ まとめ
・行きたい学校を多角的な視点から検討しましょう。
・第一志望も第二志望も、併願校も、お子様に通って欲しいと思える学校を見つけましょう。
・お子様の意思を尊重しましょう。
・第一志望校は高い目標にして、モチベーションを高めましょう。
・必ず押さえ校を決め、万が一の状況にも慌てないように対策しましょう。
・第一志望校の変更は慎重に。お子様とよく話し合って結論をだしましょう。
今回はここまで。ぜひ、最終的な志望校の決定の際に参考にしていただけると幸いです。
では、また次回でお会いしましょう。
受験Dr.吉野でした。