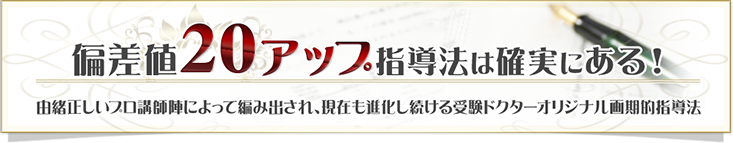こんにちは。
受験Dr.の科学大好き講師、澤田重治です。
9月も半ばを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。
まもなくやってくる秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。
季節の変わり目を知らせてくれる大切な節目です。
中学入試理科の天体関連の問題としても重要な日ですね。
そんな時期なのに……そろそろ涼しくなってほしいと思います。

ところで、私が子どもの頃には、秋になると近くの原っぱや川沿いに
たくさんの赤とんぼが群れ飛ぶ姿をよく見かけました。
夕暮れの空を赤く染めるように飛び回る赤とんぼは、
秋の風物詩そのものでした。
でも最近では、その光景を目にすることが
ずいぶん少なくなった気がします。
中学入試でも頻出の「赤とんぼ」とは?
この「赤とんぼ」、正式な名前はアキアカネといいます。
アキアカネは他のトンボと比べても特別な生活のしかたをしていて、
中学受験の理科でも頻出の題材です。
春から初夏にかけて水辺でふ化したアキアカネのヤゴ(トンボの幼虫)は、
夏の間は山あいの涼しい場所で成長します。
そして成虫になると、いったん低地に降りてきて
田んぼや原っぱで暮らすようになります。
この頃のアキアカネはまだ赤くありません。
実は、成虫になってもしばらくは褐色で、
気温が下がり始める秋になると、オスの体が真っ赤に色づいていくのです。
さらにアキアカネには、他のトンボにはあまり見られない特別な習性があります。
それは卵の状態で冬越しをすることです。
トンボのなかまの多くは、ヤゴ(幼虫)の状態で冬を越します。
しかしアキアカネは秋の終わりに田んぼや水辺に卵を産み、
そのまま寒い冬をじっと過ごします。
そして、翌春になると卵からふ化し、ヤゴとして水中で暮らし始めます。
この「卵で冬を越す」という特徴は、厳しい冬の寒さから身を守るための工夫であり、
中学受験の理科でも「昆虫の冬越しのしかた」の問題としてよく問われます。
赤とんぼを取り巻く環境の変化
私たちが子どもの頃には、たくさん飛んでいた赤とんぼ。
なぜ最近は見かける機会が減ったのでしょうか?
その理由のひとつは、農薬の使用です。
田んぼにまかれる農薬がヤゴに悪影響を与え、
育つ前に死んでしまうことがあるのです。
また、地球温暖化で山あいの気温が上がり、
アキアカネが夏を涼しい場所で過ごせなくなったことも影響していると考えられています。
赤とんぼは、ただの秋の風物詩ではなく、自然と深く関わる生き物です。
私たちが暮らす環境の変化が、昆虫たちの暮らしにも大きな影響を与えているのですね。
次回もまた、楽しくて中学受験の役に立つ、身近な科学の話をお届けします。
どうぞお楽しみに!