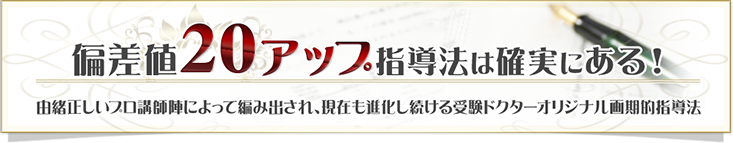皆さま、こんにちは!
前回・前々回と、「そもそも偏差値ってなに?」ということを考えています。
今回はその第3回です。
前回の最後にも書きましたが、偏差値という考え方は日本にしかありません。
中学校の理科教員であった桑田昭三先生が独自に研究・考案したものとして知られています。
今回は、考案者の桑田先生が偏差値というものをどう考えていたかについて迫ってみましょう。
なお、今回のブログを執筆するにあたり、2つの参考資料を用いています。
1つは、1976年に徳間書店から発刊された『創案者が初公開する進学必勝法 偏差値の秘密』です。
この本は桑田先生ご自身が執筆された、偏差値についての解説本です。
現在は絶版になっていますが、古書として手に入れたので、今回のブログの中でも一部引用します。
以下、『偏差値の秘密』とします。
資料の2つ目は、インターネット上で公開されているインタビュー記事です。
2010年にJALTというNPO団体が桑田先生に行ったインタビューをもとにして書かれています。
現在も公開されていますので、興味のある方は以下のURLをご参照ください。
https://teval.jalt.org/test/PDF/Kuwata-j.pdf
『偏差値の生みの親・桑田昭三氏へのインタービュー』というタイトルです。
以下、『桑田昭三氏へのインタービュー』とします。
桑田先生は1928年生まれで、2016年に他界されています。
『偏差値の秘密』の方は、「偏差値」という言葉が世の中に急速に浸透していく時代に執筆された本です。
50年以上も前の本なので、今の教育事情とはかなり異なる部分があります。
特に、偏差値に対する反発も激しかった時代で、創案者の桑田先生にもバッシングがかなりあったようです。
そんな中で、世の中の様々な誤解や無理解に対して、桑田先生自身が答えるというような内容になっています。
一方、『桑田昭三氏へのインタービュー』は先生が最晩年に何を考えていたかがわかります。
偏差値というものが世の中に完全に受け入れられ、当たり前のアイテムになった時代です。
偏差値の創案者として知られる桑田先生が、そのような時代に偏差値をどう考えていたかが語られています。
偏差値を扱う際のポイント4点
ここから先は、この2つの資料をもとに、現代の中学受験でどう偏差値をとらえるべきかを考えてみます。
ただ、結論だけを先に知りたいという方もいらっしゃると思います。
そういう方のために、ここから先のポイントだけ列挙しておきます。
以下の4点を知っておいて頂ければ十分です。
①そもそも偏差値はぶれるもので、最大で偏差値6くらいの上下は自然に起こる
②偏差値同士の比較には注意が必要で、特に同内容の試験でなければ推移を追うことにあまり意味はない
③偏差値を利用して受験の合否を判断する場合、向いている試験と向いていない試験が存在する
④偏差値はひとつの指標であって、試験内容、順位、平均点など、他の要素と総合的に考える必要がある
この4点は創案者の桑田先生のお考えをもとに、私の知識や経験も加えて解釈したものです。
それでも、長く受験指導をされているプロの塾講師のような方なら、おおむね同意して頂けるかと思います。
これ以上詳しいことが必要ない場合は、今回はこの4点だけ覚えておいて頂ければOKです。
もちろん、偏差値が勉強を進めていくうえで大切なものであり、最も信頼度が高い数値であるのが前提です。
ただ、偏差値が重要な指標であることは間違いないのですが、それだけですべてがわかるわけではありません。
特に、中学受験の合否の判定については、もっとも参考になるデータではありますが、注意が必要です。
そもそも桑田先生は、高校受験、特に公立高校の受験での合否を予測するものとして偏差値を設計されました。
私は高校受験の指導経験も10年以上ありますが、公立高校の受験においては偏差値の精度は今も抜群です。
偏差値に指導実感も加味すれば、自分の担当生徒の合否結果を95%以上の確率で当てる自信があります。
しかし、中学受験の場合は必ずしもそうはなりません。
それは偏差値が悪いわけではなく、そもそもの偏差値の設計思想と分析しているデータの相性が悪いのです。
同様のことは、大学受験においても言えます。
詳しくはまた別の機会で解説します。
ということで、こと中学受験においては、偏差値を見るときに注意が必要だということをぜひ知ってください。
特に、公立の高校受験の経験があるお父様、お母様はお気を付けください。
公立高校の偏差値と、中学受験の偏差値は別物ですし、同じような精度で合否判定もできません。
そこを理解せずに数字だけを見ていると、大きな勘違いをしてしまうかもしれません。
そのときに傷つくのはお子さんです。
お子さんの努力や頑張りを、正当に評価できていないということになるからです。
心配な場合は、お子さんの成績をどう評価するべきか、プロの先生にぜひ相談してみてください。
桑田先生とは何者か?
次回のブログで、先ほど挙げた4点のポイントを順に解説していきます。
今回は、桑田先生ご自身について、少しだけ書いておきます。
ここから先は、桑田先生ご自身と偏差値という考え方に興味がある方だけお読みください。
まず『桑田昭三氏へのインタービュー』から、桑田先生ご自身の言葉を、少し長いですが引用します。
仮に、センター試験で偏差値を用いて成績評価をしたとしても、真の学力の1点差までは、
測ることはできません。テストは、やるたびに得点が同じになるとは限りません。試験の点
数は、問題の難易度で異なりますが、学力は相対的にはほとんど変わりません。ならば、偏
差値60の生徒はいつも平均値(=50)より10ポイント高い成績が取れるような気がします。
しかし、実際にはそうなることは稀です。試験は一種の測定ですから、測定値には誤差は付
きものだからです。学力テストのような間接的な測定では尚更のことです。したがって、
その誤差をきちんと計算に入れて受験計画を立てないと、取り返しのつかない結果を招くこと
があります。私は、学力テストの測定誤差の揺れについて調査したことがあります。高校入
試関連のテストに限って言えば、偏差値で±3ぐらいの範囲で成績が変動する確率が60%前
後でした。厳密には揺れ幅は各人各様です。私でも本番のテストで取る成績の範囲と確率は
予言できますが、試験当日、実際に取れる成績は、どう知恵を絞っても予測することが出来ま
せんでした。つまり、本番の試験では、平均的学力より高い側の成績が出るのか、それとも低
い側の成績が出るのか、神様だけしか知らないということです。したがって、この闇の部分を
私は『テストの神様の裁量分』と呼ぶことにしています。
(『桑田昭三氏へのインタービュー』 5ページより、一部誤字脱字と思われる部分を改めました)
いかかでしょうか?
少し言葉が難しいところがありますが、先ほど挙げた4点のポイントに重なることも語られていると思います。
また、最後の「テストの神様の裁量分」という言葉が、とても含蓄がありますね。
これが、生涯をかけて、受験生の成績データと偏差値に向かいあい続けた桑田先生の結論なのです。
「結局は、試験結果は受けてみるまでわからん」とおっしゃっているわけです。
そりゃそうですよね、と感じる部分もありますし、生涯をかけて研究した方の言葉だからこそ重いとも感じますね。
桑田昭三先生のプロフィールも、同じ『桑田昭三氏へのインタービュー』から引用します。
桑田昭三氏プロフィール
昭和3年生まれ
長野県飯田市生まれ
上田繊維専門学校(現 信州大学繊維学部)卒業
長野県-東京都の公立中学校の理科教員として勤務 1950年4月〜1963年3月
民間研究機関において偏差値を含むテスト学の研究に従事 1963年4月〜1980年
(『桑田昭三氏へのインタービュー』 1ページより)
少し補足すると、「民間研究機関」というのは、現在の進学研究会のことです。
進学研究会は首都圏の公立高校受験で必須の模試である「Vもぎ」を実施している企業ですね。
桑田先生は学校という職場にどうしても馴染めなかったようで、13年で教員生活を終えられています。
この教師を辞めるまでの13年間のいきさつについては、『偏差値の秘密』に詳しく書かれています。
最後にひとつ、大きな勘違い(?)について書いておきます。
それは、桑田先生が偏差値そのものの考案者ではない、ということです。
ここまで読んで頂いた方なら、「えー?」となりますよね。
書籍やインタビューのタイトルにも、「創案者」「生みの親」とあるではないですか。
しかし、『偏差値の秘密』を読んでみると、実際にはそうではないようなのです。
以下、『偏差値の秘密』から引用します。
昭和32年、校長が定年で退職された後、城南中学に、西戸山中学から牛山先生という校長が
赴任してこられた。着任後、間もないころだったと記憶するが、ある日のこと、何かの話のつい
でに私はこの牛山校長に、現在私が抱えている難問、それにともなう悩みをぶつけてみた。(中略)
すると牛山校長は、意外にも「それでしたら、私の前にいた中学の社会科の先生がヘンサチと
いうものを用いて指導に当たっているようでしたよ。(中略)」と、いってくれたのである。
この校長の紹介で、それから数日たったある日の夕方、私は黒田先生という社会科の先生と、
浜田先生という数学の先生に校長室で会うことができた。これら2人の先生から、それこそヘン
サチとは偏差値と書くということにはじまって、それをじっさいにどう活用しているかなどにつ
いて教えていただいた。
(『偏差値の秘密』74ページ、数字は算用数字にあらためました)
偏差値ということばが、突然降って湧いたかのように世間の大きな話題になっている。しかし
偏差値は今にはじまったものではない。昭和26年に発刊された『統計学による新教育統計法』
(岩原信九郎著・日本文化科学社発行)によれば「Z得点もやはり標準得点というが、日本では
偏差値又は標準偏差値という」と記されている。(中略)偏差値ということばはこの時点ですで
にいいならわされていたことになる。
(『偏差値の秘密』108ページ、数字は算用数字にあらためました)
ということで、「偏差値」という概念そのものは、桑田先生以前にも存在はしていました。
それをより詳細に研究して、公立高校の受験指導に利用できる形に桑田先生がまとめたということです。
桑田先生はそのために、教員生活の合間をぬって、確率・統計・微積分などの数学を一から勉強しなおします。
このあたりのことも、『偏差値の秘密』に詳しく書かれています。
考案者かどうかはともかくとして、少なくとも日本の教育に偏差値を広めた人であるのは間違いないです。
今の日本の教育の方向性を良くも悪くも決定づけた偉人として、記憶されるべき方だと思います。
桑田先生のすごいところは、カンや経験で行っていた受験指導に科学的な視点を持ち込んだことです。
ご自身でも「受験の物理学」と表現されていますが、正確な未来予測ができないかと考えたのです。
つまり、合格・不合格を試験の前に知ることはできないか、ということなのです。
それは、教え子から一人も不合格者を出したくない、全員を合格させたい、という一心だったようです。
とかく偏差値というと、冷たい残酷な数字であるかのようにとらえがちかと思います。
しかしその裏には、桑田先生の一人ひとりの生徒を思う熱い気持ちがあったことはぜひ知っておいてください。
次回は先ほど挙げた4点のポイントについて、さらに詳しく解説します。
では、また次回お会いしましょう!