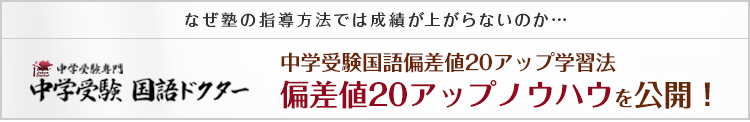こんにちは、受験Dr.の太田 陽光です。
今回は、答えを見つけるための手がかりを探す方法を知っているという、基本的なことの大切さについて書きます。
問題を解くとき、答えを見つけるための手がかりを探す方法を知っていないと不正解になることがあります。
その手がかりを探す方法のひとつめは、答えに迷ったら本文に戻る、です。
例えば選択肢問題において、あと二つに絞り込めたのだけれど、最後の判断ができないとき、
選択肢の内容だけを見て答えを決めてしまうと、正しい答えを選べないことがあります。
それは、自分の頭の中にある情報だけ、あるいは思い込みだけで答えを選んでいるからです。
そのような時は、客観的な情報を、または、新たな視点を手に入れるために、
もう一度本文に戻り、線の近くを読んでみましょう。
そのあとに、二つに絞られた選択肢を読み直し、
本文に書いてあることの有無を確認するのです。
例えば、以下のような文と問いがあるとします。
今のような状況が進めば、科学によって人間が支配されるのは間違いありません。科学の下では個々の人間性は無視され、人間のやる気を奪っていくのです。
問い 「人間が支配される」とはどういうことか
このとき、選択肢に「個々の人間性は無視され」と同じ言葉、もしくは、言い換え(例えば、人間はみな同じようになり)があるか確かめることで、正解が選べます。
本当に当たり前の、基本的な解き方なのですが、もし答えの手がかりを探す方法を知らなかった場合、この問いは落としてしまうわけです。
自分が見落とした情報を手に入れたり、新たな視点で考えたりすることが大切なのです。
ただし、やみくもに線の前後を読んでいても、答えの手がかりが見つからない場合もあります。
そこで、答えの手がかりとなる部分のあるところを推理するための言葉に注目するという、
手がかりを探す方法のふたつめが役に立ちます。
基本的なことです。
指示語や接続語などに注目すればよいのです。
例えば、本文に「この本は」とあり、問いが「本とはどのようなものですか」であったとき、
「この」という指示語がありますから、前に答えの手がかりがあると考えるでしょう。
それでよいのです。
では、本文が「しかし、この本は…」であった場合はどうでしょう。
「しかし」は逆接ですから、前には答えに求められることと反対のことが書かれている場合もあります。
その時には、「本は」と主語になっていることから、述語をおさえる、
つまり「本は」の後に答えの手がかりがあると考えることができます。
また、問いが「筆者は本とはどのようなものだと言っていますか」であったとき、
「この本」の前に、例が書いてあったなら、
例の部分を飛び越え、さらに前にある筆者の意見が書かれた部分に答えの手がかりがあると考えます。
このように、本文に戻るという当たり前のこと、つまり基本動作を、
さらには、戻った先で接続語や指示語などに注目するという基本動作を行うことで、
正解率は上がりますし、
無駄に悩む時間を削ることができるのです。
自分の解き方を見直し、もし国語の基本動作をおろそかにしていたのならばもう一度その大切さを認識して、底固い国語力を身につけましょう。