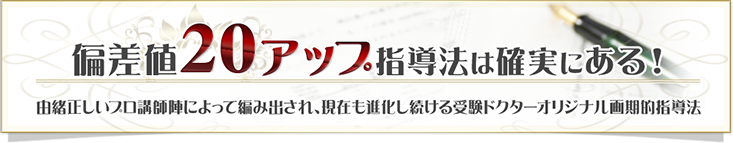皆さま、こんにちは!
「そもそも偏差値ってなに?」ということを考えていくシリーズ、今回はその第4回です。
偏差値の創案者として知られる桑田昭三先生のご意見も引用しつつ、偏差値の扱い方を考えています。
前回、現代の中学受験でどう偏差値をとらえるべきかについて、以下の4点をポイントに挙げました。
①そもそも偏差値はぶれるもので、最大で偏差値6くらいの上下は自然に起こる
②偏差値同士の比較には注意が必要で、特に同内容の試験でなければ推移を追うことにあまり意味はない
③偏差値を利用して受験の合否を判断する場合、向いている試験と向いていない試験が存在する
④偏差値はひとつの指標であって、試験内容、順位、平均点など、他の要素と総合的に考える必要がある
この4点は創案者の桑田先生のお考えをもとに、私の知識や経験も加えて解釈したものです。
そこまで詳しいことは必要ないという方は、最低限、この4点を覚えておいて頂ければ十分です。
今回は、この4つのポイントのうち、①についてより詳しく説明していきます。
なお、今回のブログでも以下の2つの参考資料を用いています。
1つは、1976年に徳間書店から発刊された『創案者が初公開する進学必勝法 偏差値の秘密』です。
以下、『偏差値の秘密』とします。
資料の2つ目は、インターネット上で公開されているインタビュー記事です。
2010年にJALTというNPO団体が桑田先生に行ったインタビューをもとにして書かれています。
現在も公開されていますので、興味のある方は以下のURLをご参照ください。
https://teval.jalt.org/test/PDF/Kuwata-j.pdf
以下、『桑田昭三氏へのインタービュー』とします。
偏差値はそもそもぶれる
偏差値は、テストの受験者の点数を統計処理して導かれる数値です。
統計処理をされているということは、それは確率的な数値なのです。
できるだけ専門的な話は避けたいので簡単に言うと、「だいたいこれくらいですよ」というおおまかな値です。
そのため、どうしてもテストごとにその数字にはぶれが出ます。
実際に創案者の桑田先生もこのようにおっしゃられています。
試験の点数は、問題の難易度で異なりますが、学力は相対的にはほとんど変わりません。ならば、
偏差値60の生徒はいつも平均値(=50)より10ポイント高い成績が取れるような気がします。
しかし、実際にはそうなることは稀です。試験は一種の測定ですから、測定値には誤差は付きも
のだからです。学力テストのような間接的な測定では尚更のことです。(中略)
高校入試関連のテストに限って言えば、偏差値で±3ぐらいの範囲で成績が変動する確率が
60%前後でした。
(『桑田昭三氏へのインタービュー』 5ページより)
「偏差値をみる場合、どんな点に注意したらよいのですか?」という質問にも以下のように答えられています。
まず第一に偏差値は、ある幅で揺れていることです。統計によって求められた数値には、
ある範囲の誤差(揺れ幅)はつきものですが、とかくあるひとつの数値だけで結論を出さな
ければ承知できないような傾向の人が多いようです。
揺れ幅をより小さく測ろうとすれば、測定の回数を重ねることによって、より確からしさ
を求めていくことが必要です。学力の偏差値を読む場合には、揺れ幅としておよそ3〜4を
みておきましょう。
(『偏差値の秘密』 194ページより)
もし±3くらいの範囲で偏差値が変動するのなら、極端な場合は偏差値が6下がることも確率的にありえます。
仮に「真の実力」が偏差値60だとします。
そして、この「真の実力」はしばらく変わらないとします。
それでも、上振れれば偏差値63をとることはあり得るということです。
そして、次のテストで逆に下振れれば、偏差値57をとることもあり得ます。
すると、この2つの結果だけ見れば「偏差値は6下がった」ということになりますね。
しかし、この場合はあくまで確率的に変動しただけで、実際の実力は変わっていないのです。
パニックにならないために
「偏差値が6も下がった」となれば、普通はびっくりします。
「一体なにが起こったんだ?」と感じるのが自然でしょう。
しかし、もし先ほどのような状況だとすると、びっくりするようなことは起こっていないのです。
単に、上振れた後に下振れただけ、です。
そもそも、実力はそんなに簡単に上下するものではありません。
急激に上がるようなこともなければ、急激に下がることもないのです。
それでも、数字上はそう見えることが起こり得ると知っておきましょう。
それだけで、偏差値を見るときの感覚が少し変わります。
もちろん、何かしらの原因で実力が発揮できなくなっている、というケースも考えられます。
また、周りと比べて相対的な実力が下がっている、ということも当然あり得ます。
しかし、本当にそうなのかは、注意深くチェックしてみる必要があるということです。
下手をすると、心配しなくてもいい状況なのに、不必要にパニックになり、誤った対応をするかもしれません。
そうなると、逆効果なことをしてしまい、余計に結果が下がってしまうことも考えられます。
お子さんが必要以上にショックを受けているときは、「大丈夫!」と大人が自信を持って言えることが重要です。
そのためにも、大人の方は冷静に数値を受け止められる知識を身に付けておきたいです。
また、相談ができる経験豊富なプロの先生を、身近な存在として持っておくことも大切です。
実力をどうとらえるか
6年生の後期ともなると、毎月のように模試が続きます。
そのときに、どうしても1回1回の結果に一喜一憂しがちです。
しかし、本当に重要なことは、次のテストに向けて何をするべきか、です。
そして、もっと重要なことは、志望校の合格に向けて何をするべきか、です。
それを知るための模試であり、模試の結果では合否は決まらないので、冷静に結果を分析することが重要です。
とはいえ、「じゃあ、子どもの客観的な実力をどう判断したらいいの?」となります。
先ほど「真の実力」という書き方をしましたが、それこそが知りたいというのが、私自身も本音です。
複数回の模試の偏差値をどうとらえるべきかについて、桑田先生は以下のように述べられています。
テストの偏差値が、7月-62、9月-53、10月-54、11月-55、12月-56
という場合に、期待できる学力をどうとらえるべきか。
ⓐ単純に平均して56と見るか、ⓑ極端に高い7月の62を除いて平均して54とするか、
ⓒ最高と最低を除いた平均の55とするか、ⓓ上からも下からも2番目の値をとって55と
するか、ⓔ上から4番目の54とするか見方によってマチマチである。平均的に期待できる
学力としてはⓓとするのがよい。測定回数が少ないときに、単純平均をとると、極端な値に
左右される危険がある。
ほぼ確実に期待できる学力としてはⓔがよい。(中略)一般的には小さい人でプラス・マイ
ナス2点、大きい人でプラス・マイナス4点の揺れを見ればよい。この例の場合は、揺れの
計算によれば、偏差値52〜56の範囲の偏差値を10回のテストの中で9回とるというこ
とになる。
平均的な学力偏差値というのは2回に1回はそれ以下の偏差値をとるという意味である。
また、この程度の測定回数の結果から、〝成績が上がり調子だから、56または57を期待
できる〟と読むようなことは誤りである。受験校を選ぶときの大事なことである。
(『偏差値の秘密』128〜129ページ、一部表記をあらためました)
個人的には、ⓒ最高と最低を除いた平均の55とする、でもいいかなと感じます。
おそらくⓒとⓓについては、同じ値になる可能性が高いと思います。
ⓔについては、より安全を見るなら、という感覚だと思います。
また、桑田先生はこのようにも述べられています。
たとえばお子さんが過去に受けたテストで偏差値63、54、57、50をとったとします。
ここで平均点をとり「ウチの子の偏差値は56です」というようにとらえてしまうのは誤りで
す。偏差値は、子どもの学力を推し測るひとつの目安ですから、上からも下からもほぼまん中、
この場合だと特に高い63と特に低い50は除いて、54〜57ぐらいというように幅をもっ
てみることです。そして揺れ幅をもう少し大きくとるとすれば、58〜52がお子さんの学力
の位置というように見るのがよい見方でしょう。
人はだれでも下のほうの成績には目をつむり、いちばん高い成績の方を信じたがるものです。
しかし、入学試験というのはもっと冷酷なものです。63の偏差値をとったことがあるから、
といってそのまま通用するものでもありません。志望校を選ぶ際にも、この偏差値の読み取り
方によって思わぬ結果を招くことがあります。
(『偏差値の秘密』188〜189ページ、一部表記をあらためました)
「58〜52」と書かれているように、やはり最大で6くらいの上下は考えた方がよいということです。
6年生は夏期講習が終わった9月から、毎月のように模試が続きます。
そのときに、今回のような数字の見方をぜひ参考にしてください。
くれぐれも数字に振り回されすぎないようにお気を付けください。
次回はポイント②について、詳しく解説します。
では、また次回お会いしましょう!