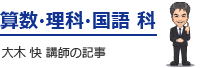今回は、サンゴに関する問題を扱います。
サンゴという生き物は、知ってるようで、ほとんど知らない生物の典型ではないでしょうか。入試問題を材料に、押さえるべき知識を確認していきます。
【問題】(2025 青山学院中)
近年、世界のサンゴ礁において、サンゴの白化現象が確認されています。サンゴの白化現象の説明として、適切なものを選びなさい。
ア 本来その地域には生息していなかった白色のサンゴだけが増える現象
イ 台風などにより舞い上がった白色の砂に、サンゴがおおわれる現象
ウ 海水中の二酸化炭素の濃度が上昇することで、サンゴが死んでしまう現象
エ サンゴの天敵であるオニヒトデが増えることでサンゴが食べられ、サンゴの骨格が見えるようになる現象
オ 海水温の上昇により、サンゴと共生する藻類がいなくなり、サンゴの骨格が見えるようになる現象
父:サンゴって、見たことある?
良夫:直接見たことはない。いろんな色で海底に広がっている様子はなんとなくイメージできるけど。
父:サンゴって、動物?植物?
良夫:海底でゆらゆら揺れているイメージだから、わかめや昆布と同じかな。
父:確かに似ている。植物っぽいイメージだよね。だけどサンゴは…動物なんだ。
良夫:えーっ。海底に鮮やかに広がっているイメージだったけど、あれは動物なんだ。
父:刺胞動物といって、イソギンチャクやクラゲの仲間なんだよ。
良夫:確かにみんなゆらゆらしている。動物であることは分かった。
父:サンゴにはいろんなタイプがあって種類も豊富なんだ。
サンゴの骨格は炭酸カルシウムでできている。何を材料にしているかな。
良夫:炭酸カルシウムだから、水中の二酸化炭素?
父:正解!
良夫:石灰岩の主成分は炭酸カルシウムで、サンゴや貝殻の体が元になっていることは習った。
水中の二酸化炭素を利用しているということは、地球温暖化抑止に貢献しているわけだね。
父:うむ。サンゴが損なわれることは、温暖化につながるね。
ところで、サンゴは藻の仲間である「褐虫藻」と共生しているんだ。
良夫:どんな関係なの?
父:褐虫藻は光合成で作った栄養を与え、サンゴは住みかを提供している。
良夫:ってことは、この問題では褐虫藻がキーポイントになるね。
父:ああ。
良夫:ここで海水温上昇によって不都合なことが起こったと。
父:褐虫藻がサンゴの体内から抜け出してしまうようだ。
良夫:じゃあ答えはオかな?
エの、ヒトデに食べられてるっていうのも聞いたことがあるけど。
父:そうだね。ただ、ヒトデの食害は白化現象の原因ではないから、除外。
良夫:じゃあオが正解だね。
温暖化の影響、恐るべし。
今回押さえておきたいことをまとめるとこうなります。
覚えておこう
サンゴは、炭酸カルシウムの骨格を持つ動物であり、褐虫藻と共生している。
温暖化により白化が進んでいる。
いかがでしたか。基本的なことさえ押さえておけば、知識なしで臨むより、一気に答えやすくなりますね。
次回もお楽しみに。