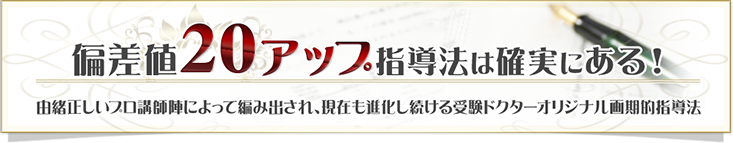皆さんこんにちは!
受験Dr.社会科の清水栄太です。
今回は2025年中学受験時事問題に関連した「関税」の第2弾をお伝えします。
前回の記事では、①関税とは何か②関税の目的③関税の国ごとの違い④関税の長所と短所についてお伝えしてきました。
今回の第2弾では、さらに深掘りして、関税の歴史について振り返ってみたいと思います。
本記事を活用して、ご家庭での学習にお役立てください!
それでは早速見ていきましょう!
第1弾でもお伝えしましたが、関税とは輸入品に対してかかる税のことでしたね!
言い換えると、外国から商品が入ってくるときに国が徴収する「税金」のことです。
では、関税はいつごろから始まったのでしょうか?
実は、関税の歴史は非常に古く、
ヨーロッパや中東では紀元前の時代から、交易路を通過する時に通行税や入国税のような形で徴収されていたとされています。
交易路にある関所で、ラクダやロバに乗せられた絹や香辛料をはじめとする貴重品が通過する際、役人が税を徴収していたそうです。
当時の関税は、その国の重要な収入源となっていたそうです。
5世紀ころから15世紀ころのヨーロッパでは、
領主や都市ごとに独自の関税制度を設け、領地を通過する商品に税金をかけていたそうです。
領地ごとに税をとられるなんて、当時の商人も大変だったことでしょう…。
17~18世紀になると、近代国家の形成とともに関税は国の重要な政策ツールになりました。
特に有名なのが「重商主義」という考え方です。
「重商主義」とは、「できるだけ多くのお金(金や銀)を自国に集めることが国を豊かにする」という考え方です。
そのために、外国からの輸入品には高い関税をかけて入りにくくし、自国の製品の輸出を促進しました。
自分のお小遣いをできるだけ増やすため、友達におもちゃを売るけど、友達から買うのは控える、といった感じです。
一方で、19世紀に入ると、特にイギリスを中心に「自由貿易」の考え方が広まりました。
「国と国の間で商品の行き来を自由にした方が、みんなが豊かになる」という考え方です。
1846年、イギリスは「穀物法」を廃止し、外国からの穀物への関税を大幅に引き下げました。
これは自由貿易への大きな一歩でした。
ですが、20世紀に入ると状況は一変します。
世界大戦が行われていた時代には、各国は自国の産業を守るために再び高い関税を課すようになります。
特に1929年の世界恐慌後、アメリカは「スムート・ホーリー関税法」という高率関税法を制定。
高関税によって国内産業を保護しようと考えましたが、結果的にはアメリカ向けの輸出が減少し、世界恐慌が悪化する要因となりました。
また、アメリカ以外の国々も、報復措置として関税を上げた結果、世界の貿易は大幅に縮小してしまいました。
第二次世界大戦の終戦後、「こんな失敗を繰り返してはいけない」と、1947年に「関税と貿易に関する一般協定(GATT)」が署名され、1948年に発効しました。
GATTは国際的な話し合いを通じて、少しずつ関税を下げていこうという取り組みです。
GATTは1995年に「世界貿易機関(WTO)」に発展しました。
WTOは、自由な貿易を目指して活動する機関で、現在も世界の貿易ルールを決める重要な機関として機能しています。
WTOについては、授業で学んだお子さんも多いはずです。
そして現代では、国と国の間で
「自由貿易協定(FTA)」や「経済連携協定(EPA)」が結ばれ、
特定の国との間では関税を下げるという柔軟な制度を採用しています。
日本は、2002年にシンガポールとのEPA締結以降、東南アジアの国々、オーストラリア、EUなどとEPAを締結しています。
例えば、日本とオーストラリアのEPAにより、オーストラリア産の牛肉の関税は段階的に下がっています。
関税は、国の利益を守るために必要な制度でもあり、時に国際的な対立の火種にもなってきました。
今回のアメリカの関税もその一つです。
関税は、歴史の中でそのあり方は何度も見直され、いまも変化し続けています。
日々のニュースや時事問題には、こうした背景がたくさん詰まっています。
「なぜ今こんなことが起きているのか?」と考えることで、暗記だけではない、社会科の楽しさが見えてきます。
今回の記事をきっかけに、時事問題への関心を少しずつ広げていってくださいね!
今回はここまで。
それではまた次回お会いしましょう!
応援しています!