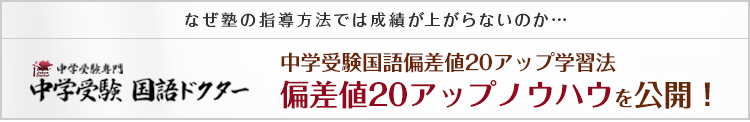みなさん、こんにちは。
受験Dr.の佐倉です。
立夏が過ぎ、暦の上では夏が始まりましたね。
立夏とは二十四節気のうちのひとつで、夏の兆しが見え始める時期のことです。他の季節にもそれぞれ立春、立秋、立冬があります。
立春の前日は節分ですが、実は、もともと立春以外の立夏、立秋、立冬の前日も節分と呼ばれていました。
立春は昔の暦では一年の始まりだったので、その前日である節分は大晦日にあたります。新年が良いものになるよう邪気を払う行事を行っていたのが、現在まで残っているのです。
また、立春と名前が似たものに春分がありますが、全く別のものなので注意しましょう。
立春は季節を分けるものであるのに対し、春分は太陽の出ている昼と出ていない夜の時間が等しくなる日を指します。秋分も同様ですが、夏には昼の時間が一番長い日を指して夏至と呼び、冬には夜が一番長い日を指して冬至と呼びます。
今年の夏至は、6月21日だそうですよ。
さて、本日は説明的文章の問題を答えるときに大切なことについてお話しします。
それは、本文のどのあたりに何について書いてあるのかを把握しておくことです。
よく意味段落分けやブロック分けをしましょうと言われるのは、これが理由です。
極端な話ですが、問題で聞かれていることが話題になっていないところに答えは書かれていません。
インターネットの検索と同じようなものです。
例えば、札幌市の天気が知りたいときに東京都内の天気予報のページを探しても、知りたい情報は載っていませんよね。みなさんならきっと、天気予報のページから北海道を選び、札幌市の天気のマークを確認するはずです。
情報の全体から、知りたいことに関連する言葉を手掛かりにして探す範囲を絞り、目当ての情報へ少しずつ近づいていく。
説明文でも論説文でも、基本的にはやることは一緒です。
答えに悩んだら、まずは設問の内容と同じ話をしているところを本文の中から探してください。
設問の内容と同じ話をしているところというのは、簡単に言うと、設問に関連する言葉、特に設問に出てくる名詞や似た意味を持つ名詞が使われているところです。
もちろん、同じ言葉が使われているからといって必ず同じ話をしているとは限りませんが、基準のひとつとして参考にしてください。しかも、問題で出される際には基本的に本文のテーマは一貫しているので、かなり高い確率で同じ話をしています。
立夏や春分の話を冒頭でしましたが、それがこの前後の内容と全くの別物だというのは、みなさんにもわかると思います。それどころか、立夏という言葉を目にして「何の話?」と思った方もいるのではないでしょうか。
出てくる言葉によって話が関連しているかどうかを判断していることがわかると思います。
傍線部の近くに答えが書かれていることが多いのは、傍線部分とその前後で、話が連続していることが多いからです。
反対に、傍線部に関連する言葉がいくつも出てくるところがあれば、傍線部から離れていても話が関連している可能性があります。
設問の内容と同じ話をしているところを見つけたら、答えを書くよりも先に、それがどこまで続いているのかを確認しておきましょう。特に、ページの終わり部分が範囲にあたる場合は、次ページの最初の部分も読んでください。見落としによる失点を防ぎましょう。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。