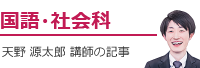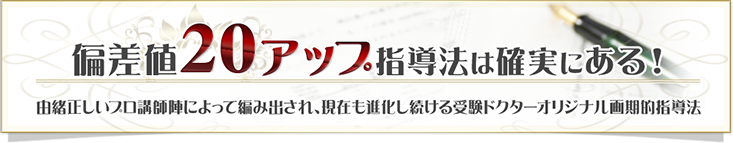みなさんこんにちは。受験Dr.国語・社会科の天野です。
今回は、公民分野頻出の国会の仕組みについての第3弾。前2回で扱った「衆議院の優越」を簡単にまとめた後、これとセットで覚えるべき衆議院の優越が適用されない3つについて扱いたいと思います。
いつものように、先生と生徒2人の会話形式でお届けします。
衆議院の優越が認められる3種類のまとめ
太郎 「情(ジョウ)ないよ。情ないよ…」
花子 「太郎君、その語呂合わせブツブツ言うのちょっと怖いよ。誰かに恨みでもあるみたい(笑)」
太郎 「え?まあ、そう言われてみれば、模試の非情な採点には恨みが…」
先生 「何があったんだ?」
太郎 「衆議院の優越が認められるものの一つに「予算の決議」と書いたらバツをくらったんです。「議決」と「決議」なんて辞書引いても同じような意味になってるのに、ひどくないですか?」
先生 「気持ちはわかるけど、法律用語は厳密に使い分けることが多いから、それは仕方ないかな。先生もこのブログを書くときは細心の注意を払うようにしてる。「議決」は議会が賛成か反対かを決定する行為のことで、「決議」は議会の何らかの意思を表明したもののこと。憲法では「議決」という言葉は何回も出てくるけど、「決議」という言葉は内閣不信任か信任の「決議案」という言い方しか出てこない。「内閣不信任決議案の議決をする」という例文で覚えてくれるといいかな。」
太郎 「なるほど。…ところで「このブログ」って何ですか?」
先生 「あ…いや、なんでもない。つい中の人が出てきてしまって…」
花子 「中の人??先生実は精巧な着ぐるみかなんかですか?!」
先生 「なわけあるかい(笑)まあ…それは置いといて、決議と議決の記憶違い以外は全て覚えられた?」
太郎 「はい!「衆議院の優越」が認められる3種類は以下です。
①そもそも衆議院にしかないもの
→内閣不信任(決議)案の議決、予算の先議権
②参議院と意見が対立した時に衆議院で再可決すれば成立するもの
→法律案の議決(※出席議員の3分の2の賛成で成立)
③両院協議会で解決しない時は再可決も必要なく衆議院の議決のまま成立するもの
→条約の承認、内閣総理大臣の指名、予算の議決 (※「情 ない よ」のゴロ)
衆議院と参議院が対等なもの
先生 「すばらしい。そしたら、衆議院の優越が適用されない、両院が対等の3つは覚えているかい?」
太郎 「そう来ると思ってましたよ!憲法改正と、弾劾裁判所の設置と…えーっと…あと一つが…」
花子 「国政調査権!!」
先生 「二人の共同作業でなんとかなったな!…と言いたいところなんだけど、少し気になるところが…」
憲法改正の発議
花子 「…あ、「憲法改正」は国会だけで決められないから、「発議」をつけて「憲法改正の発議」にしないといけないとかですか?各議院の総議員の3分の2の賛成で発議されたら、国民投票をして過半数の賛成が必要なんですよね。」
先生 「その通り!ところで憲法改正の発議はなんで対等なんだろうね?」
太郎 「ヒント下さい。」
先生 「せめて一瞬くらい考えるフリはしてくれ(笑)」
太郎 「あ、いや最近僕の勉強できないキャラが崩壊してきてるんで…初心にかえろうかと思って(笑)」
先生 「かえり方が間違ってる気がするが…ヒントといえば、衆議院の優越が適応される時の基準を考…」
太郎 「直近の民意(最新の国民の意見)やスピードが大事かどうかですね?」
先生 「今度は賢すぎるスピードになってるぞ(笑)」
花子 「…てことは、衆議院と参議院が対等なものは、直近の民意やスピードをあまり重視しない。長い目で見て慎重にやるべきものってことですか?」
先生 「御名答。じゃあ、憲法改正を慎重にやるべき…」
太郎 「…なのは、法律よりも上にある最上位のルールだから!」
先生 「質問を最後まで聞いて(笑)正解だけれども。そういう憲法の性格のことを四字で何と言う?」
花子 「戦争放棄じゃなくて、最高法規。だから変えにくくなってるわけですよね。」
太郎 「例えば衆議院で5分の4でも参議院で5分の3ならだめとか、そもそも厳しいですよね。」
先生 「うん。ちなみに変えにくさは国によって違っていて、日本のはかなり改正しにくい方なので、硬い憲法ってことで硬性憲法って言われたりもするよ。」
憲法改正と歴史
太郎 「戦後一度も改正されてないんですもんね。」
先生 「一度改正されかけたことはあったけどね。」
太郎 「えー?!」
先生 「その「えー?」は、本当にわかっていないのか?(笑)」
太郎 「わざとらしすぎましたか(笑)いや、ちゃんとは覚えていないんですけど、確か自由民主党(自民党)は憲法改正を目指して結党されて、あとちょっとで3分の2の勢力になりかけたんですよね?」
先生 「その通り。憲法改正を目指したきっかけは何だったの?」
花子 「いろいろあると思いますけど、1950年の朝鮮戦争がきっかけでそれまで日本を占領していたアメリカの方針が変わり、日本を資本主義陣営として独立させて最小限の防衛力も自前で持たせようとしたために警察予備隊が置かれて、最終的に1954年に自衛隊になったことですよね?」
先生 「やっぱり花子さんすごいな…(笑)」
太郎 「自衛隊が憲法9条に反していないかわかりにくいところがあるんで、9条を改正してその存在をきちんと書こうとした人びとが、衆議院と参議院ともに3分の2以上をとれるような巨大政党を作ろうとしたってことですよね?結局ぎりぎり3分の2は獲得できなかったけれど、巨大な単独与党ができて、それ以降55年間政権を担当しつづけた…これを55年体制と言う」
先生 「太郎くんもやはり負けじとすごい…と言いたいところなんだけど、最後だけ違うぞ(笑)」
太郎 「え、55年体制であってますよね?」
先生 「うん、55年体制という言葉はあってるけど、55年間政権を担当したからじゃなく、1955年に始まったから55年体制と言うんだよ…結構勘違いしている人がいるんだけど。」
太郎 「そうだったんですね。そういえば1993年に細川連立内閣ができて55年体制が崩壊したんだから、40年弱ですもんね…」
先生 「最近では自民党の安倍政権が憲法改正を本気で目指していた感じがあるけど、結局2007年に国民投票法を成立させて憲法改正原案について話し合う憲法審査会の設置はしたものの、改正自体には至らなかったね。」
花子 「国民投票法ってなんでしたっけ?」
先生 「国会によって発議された後で国民投票をする時の手続きを決めた法律だね。」
花子 「そうでした。それが決まったのがこんなに最近なんだって驚いた覚えがあります。」
太郎 「ところで、衆議院の優越が適用されない憲法改正の発議以外の2つ、弾劾裁判所の設置と国勢調査権も、やはり憲法改正と同じくスピードを重視せず慎重さが大切なものってことですかね?」
先生 「その通りだね。ただ、その2つについてはそこまで深く問われることはないものの、司法権(裁判所)の復習ともからむし、ややこしくて面白い問題も含んでるから、次回に回すことにしよう。」
太郎 「えーー。ややこしくて面白いとか先生また僕達をいじめて楽しむ気でしょう(笑)今回教えてくれないかわりに、衆議院と参議院が対等の立場の3つをまとめるゴロとかがあれば先に教えてください。」
先生 「…仕方ないな。最近太郎君頑張ってるし、頭文字をとっただけであまりうまくないけれど…

でどうだい?」
花子 「なんですかこの「対等なのは子どもの時だけだよ」みたいな、平等権に反するようなゴロは…」
先生 「すみません…」
いかがでしたか。というわけで、衆議院の優越が適用されず衆議院と参議院が対等の立場となる残りの2つについては、司法権との関係もあわせて次回扱いたいと思います。
それではまた、お会いしましょう。