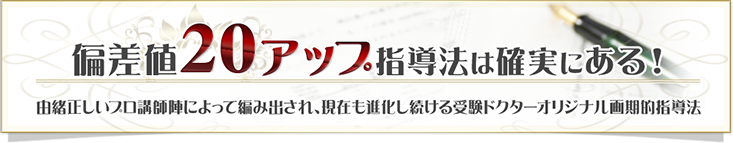皆さんこんにちは!
受験ドクターの清水栄太です。
無類のカレー好きの私にとって、
2024年から今年にかけての米の値上がりは、深刻な問題でした。
カレーパスタにも挑戦しましたが、やっぱりカレーはごはん!
と感じています。
私たちの生活に欠かせない「お米」ですが、5月〜6月には政府による備蓄米の放出などが大々的に報じられていましたね。
そこで今回は、中学受験の時事問題として取り上げられそうな
「お米」と日本の農業について、お伝えします。
❶お米はどうやって作られるの?
まず、土づくりや育苗(いくびょう)を行います。
その後、田起こしを行い、田んぼの土をトラクターで耕してやわらかくします。
次に、水を張って代かき(しろかき)をし、田植えを行います。
最近は田植え機を使うことが多いですが、昔は家族総出で、手作業で行われていました。
田植えが終わると、稲が育つ間、農家の人たちは水の管理に細心の注意を払います。
常に適切な水位を保つ必要があります。
その後、中干しを行い田んぼの水を抜きます。
この作業を行うことで、根を強く張るようにし、酸素を補給し根腐れを防ぐなどの利点があります。
夏の暑い時期に稲の花が咲き、やがて穂が実ります。
秋になると、いよいよ収穫の時期です。
コンバインという機械で刈り取り、その場で脱穀(だっこく)まで行います。
昔は鎌で刈り取り、天日干しをして、足で踏んで脱穀していたのですが、今ではずいぶん効率的になりました。
収穫されたお米は、籾(もみ)の状態から籾殻(もみがら)を取り除いて玄米にし、さらに精米して、私たちが食べる白米になります。
一粒のお米ができるまでには、農家の人たちの半年以上の努力が詰まっているのです。
❷農業を変えた1940年代以降の法律や制度
1940年代以降、日本の農業は大きく変化しました。
特に重要な法律や仕組みを簡単に紹介します!
まず1942年に制定されたのが食糧管理法です。
戦時中の食料不足に対応するため、お米の生産から流通までを国が管理する仕組みが導入されました。
農家は決められた量のお米を国に売り、国が価格を決めて消費者に販売しました。
戦後の1947年には農地改革が行われました。
それまで地主が持っていた土地を、小作人に安く売ることで、
「自分の土地で農業をする」自作農が増えることになりました。
1970年代には、食の多様化が進み、米の消費量が減少しました。
そのため、米の作りすぎを防ぐ目的で減反政策が始まりました。
田んぼを休ませる休耕や、他の作物に切り替える転作によって、生産量を調整する仕組みです。
(この制度は2018年に終了しました。)
その後、1995年には食糧管理法に代わって新食糧法が制定されました。
これによりお米の流通が自由化され、農家が自分で価格を決めて販売できるようになりました。
さらに2007年には「農地法」が改正され、株式会社などの法人も農業に参入しやすくなりました。
最近では、IT企業が農業に参入するケースも増えています。
❸お米の生産のさかんな地域
日本でお米の生産が盛んな地域を、ランキング形式で見ていきましょう。
第1位:新潟県
越後平野を中心に、コシヒカリが有名です。
信濃川流域の肥沃な土地、雪解け水、昼夜の寒暖差が美味しいお米を育てます。
第2位:北海道
石狩川流域の石狩平野や上川盆地を中心に、ゆめぴりかやななつぼしといった品種が生産されて
います。北海道は広大な土地を活かした大規模農業が特徴です。
第3位:秋田県
秋田平野を中心に、あきたこまちの産地として知られています。
この他にも、
山形県の庄内平野(最上川流域)、宮城県の仙台平野、茨城県など、
各地で米の生産がされています。
白地図で場所をイメージできるようにしておくと良いでしょう♪
❹備蓄米の放出
2024年、お米の価格が大幅に上昇し、令和の米騒動とも呼ばれる事態が一部で話題となりました。
前年の不作、インバウンド需要の増加、さらには南海トラフ地震の臨時情報による一部地域での買い占めなど、複数の要因が重なったことが原因とされています。
価格はその後も上昇し、2025年3月には5kgで4,000円を超えました。
こうした状況を受けて、政府は異例の措置として備蓄米の放出を決定しました。
この制度は、1993年の大凶作を受けて1995年から始まったものです。
通常、備蓄米は不作のときにのみ放出されますが、今回は流通段階での品薄が原因だったため、異例の対応となりました。
まとめ
お米は私たちの生活に欠かせない主食ですが、
その裏には農家の方々の努力、長い歴史、そして複雑な制度と流通の仕組みが存在しています。
これからも安定してお米を食べ続けるためには、農業の大切さを理解し、
食べ物を大切にする心を持ち、消費者としての視点も育てていくことが重要ですね。
何気なく食べているごはんにも、少しだけ目を向けてみてください。
「このお米はどこで作られたのかな?」
「どうして最近ちょっと高くなってるんだろう?」
そう考えることが、社会や時事問題への関心を高め、
日本の農業や食の未来を守る一歩につながるかもしれません。
今回はここまで。
また次回お会いしましょう!
応援しています!