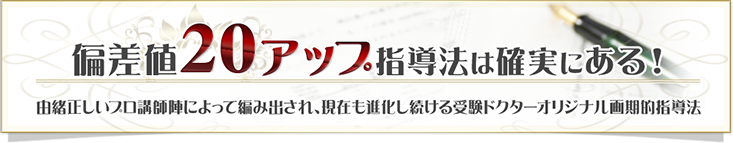こんにちは。
受験Dr.の吉野です。
「家庭学習のスケジュールをどう立てたらいいか分からない」
「がんばって家庭学習をしているけど成績が上がらない」
そういったお悩みの声をよく聞きます。
今回は、「家庭学習はどうやればいいのか?」というお悩みに答えていきます。
1 家庭学習の重要性
塾に通うだけでは成績は上がりません。家庭学習が大切です。なぜなら、塾での学習時間より家庭学習での学習時間の方が圧倒的に多いからです。では、家庭学習では何をしたらいいでしょうか?ずばり 「解きなおし」 です。具体的には、学んだことを思い出して解答を作る練習です。指示された宿題を解いて解説を読むだけでは力は付きません。自力で解けるまでやり込むことが大切になります。
家庭学習は習ったことを身につけるために必要不可欠な作業です。基本的にはご家庭で実施するものですが、前提となる「習ったことが分からない」などがありましたら、プロの講師の力を頼って、基本原理を理解してから家庭学習に取り組みましょう。
2 家庭学習は親が管理する
学習スケジュールは親が立てて、実施したかどうか管理してください。中学生以上になれば、何をどうやるかは子どもに任せて構いません。しかし、小学生の場合、家庭学習のやり方を知らないので、自分で計画を立て実行する力がありません。ですから、正しい家庭学習のやり方を教える必要があります。最初のうちはしっかりとサポートし、習慣化ができてきたら子どもに任せていきましょう。
また、親が細かいところまで見る必要はありません。やることは
1 時間指示
2 内容指示
3 ○付け
4 実施の確認
4つだけです。1週間の学習スケジュールを作成し、張り出し、子どもに実施状況を記入させてください。可能なら親が解説をしても良いですが、無理に行う必要はありません。むしろ子どもが自分で調べて、理解する練習をさせた方が効果的です。どうしても分からない単元はプロの講師に聞きましょう。
次からは、学習スケジュールの立て方、家庭学習のやり方、のポイントを具体的に上げていきます。
3 学習スケジュールの立て方
以下の4つのポイントに注意して1週間の学習スケジュールを立てましょう。大切なのは「習慣化」です。毎日やることを決めて習慣化していけば、無理なく学習が継続できます。
(1)学習時間の目安
一般的な学習時間は下記のようになります。塾での学習時間もここに含まれますので、この時間から塾の時間を除いた時間で家庭学習のスケジュールを立てましょう。
小4・小5・・・平日:1~3時間、休日:3~5時間
小6・・・平日:3~5時間、休日:8~10時間
(2)睡眠時間
学年が上がると学習量も増えるため、睡眠時間を削ってでも勉強しようとがんばるお子様を見かけますが、やめてください。睡眠が足りないてないと頭が働かなくなり、記憶が定着しにくくなります。また、睡眠不足が続くと、体力・、免疫力が低下して風邪をひきやすくなります。睡眠時間はしっかり確保しましょう。理想的な睡眠時間は9時間です。夜10時に就寝して、朝7時に起床するのがお勧めです。
また、スマホやゲーム機のディスプレイから発せられるブルーライトが睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌に悪影響を及ぼす可能性が報告されています。そのため、就寝2時間前、夜の20時以降はスマホやゲーム機を使用しないようにしたほうがよいでしょう。
(3)朝学習
朝学習は必ずやりましょう。脳はその日に起こったことを睡眠中に整理すると言われています。よって、朝は昨夜学習したことが眠っている間に整理されているので、頭がスッキリした状態で学習に取り組むことが出来ます。朝学習後に朝食をとり、学校へ向かいます。学校への通学時間が長い方は、起床時間を早めるなどしてください。最低でも30分の朝学習の習慣をつけましょう。朝7時に起床して、30分間勉強するのがお勧めです。
(4)時間で区切って、延長しない
50分やって10分休憩を1単位として、60分ごとに学習内容を決めていきましょう。予定した内容が時間内で終わらなかった場合でも延長はしないでください。時間ごとで学習内容を区切っていき、終わらなかった場合は、別時間帯または別日で残りを行いましょう。スケジュールの修正は親が随時行ってください。
4 家庭学習のやり方
家庭学習をやる上で、特に注意するポイントを6つ上げます。
(1)解きなおしを必ず行う
1つの単元を3周まわしましょう。ほとんどの方は1周目で終わっています。成績の上がらない子どもは2周目以降の解きなおしができていない、やり方が甘い、ことが多いです。もちろん、学習量が多い場合はやる問題を絞ってください。テキストの問題を全てやらなければいけない訳ではありません。どの問題を優先してやるかは、塾の先生に相談すると良いです。
1 1周目・・・授業を思い出しながら解く。しばらく考えてもわからないときは、解きなおしにまわす。
2 2週目・・・①で解けなかった問題、間違えた問題の解きなおし。テキストやノートなどを見て、調べて、自分で解答を作る。ただし、解答・解説は見てはいけない。
3 3周目・・・➁で間違えた問題の解きなおし。解答・解説を読んで理解したら、解答・解説を見ずに解きなおしを行う。
※ ③で解けない、わからない問題があった場合は、塾の先生に質問してください。
(2)復習は48時間以内
塾の宿題は授業後48時間以内に、家庭学習の直しも前回から48時間以内に実施してください。記憶を残すため、忘れないうちに前回の記憶を上書きしましょう。
(3)目標を数値化して決める
今週の家庭学習の目標を決めましょう。その際、目標は数値化してください。
× 解きなおしをがんばる
○ 解きなおしで正答率80%以上
親は、この目標数値で子どもを評価してあげましょう。具体的でない目標だと、評価する人の主観が入ってしまい、お互いに不満が残ります。数値だけで客観的に評価すれば、何をすれば評価されるかが分かり、モチベーションを上げやすいです。
(4)スケジュールを可視化して共有する
紙に1週間分のスケジュールを書いて、冷蔵庫など見える場所に貼っておきましょう。家庭学習を実施したら、チェック印を子どもにつけさせます。親は進捗状況を確認して、修正が必要なら随時書き換えます。さらに次の1週間分のスケジュールを立てて貼ります。アプリでの管理でも良いですが、お手軽に修正ができ、みんなが見られるので、紙での活用をお勧めします。
(5)就寝前に家庭学習を全て提出
子どもに、本日実施したテキスト、ノートを就寝前に提出させます。親は「○付け」をして明日の朝に返却してください。忙しくて○付けができない場合はそのまま返却しても構いません。大切なのは習慣化で、毎日同じことをくり返すことを意識させてください。
(6)解答・解説は親が保管
解答はすべて親が保管してください。3周目(解きなおし2回目)で解答・解説を読んで理解する時のみ子どもに渡してください。子どもを信頼していない訳ではありません。他人が採点することでより客観的に書く練習になります。
5 まとめ
・家庭学習は、親の管理のもと、解きなおしに力を入れましょう。
・家庭学習のルールを決め、ルールに従って同じルーティーンをくり返していきましょう。
・睡眠時間はしっかり確保し、朝学習を行いましょう。
今回はここまで。家庭学習が効果的に実施できることを期待しています。
では、また次回でお会いしましょう。
受験Dr.吉野でした。