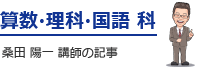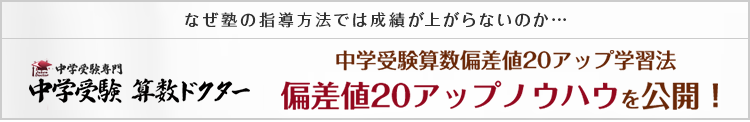みなさん、こんにちは。受験Dr.の桑田陽一です。
9月の講師ブログをお届けします。
今回は、2025年2月25日に行われた京都大学の入学試験から前回に続いてもう1題紹介します。
前回は文系学部の問題でしたが、今回は理系学部を目指す受験生が取り組む数学の問題です!
問題
正の整数x、y、zを用いて
N=9z^2=x^6+y^4
と表される正の整数Nの最小値を求めよ。
(2025京都大学 理系 大問2)
「z^2」という記号は見たことがない人が多いでしょう。
「zを2個かけ合わせた数」、つまり「z×z」のことを表します。
同じように、「x^6」は「xを6個かけ合わせた数」、「x×x×x×x×x×x」のことを表し、「y^4」は「y×y×y×y」のことを表しています。
アルファベットの「x」と、掛け算の記号の「×」が入り交じって分かりにくいので、問題の内容を変えずに中学受験生向けの表現に書き換えてみます。
問題(改)
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができる整数Nのうち、最も小さいものを求めなさい。
これで、中学受験生も問題の意味が理解できるようになったでしょう。
意欲のある受験生ならこのままでも解けないことはないのですが、実のところ、これは優秀な高校生にとってもかなりの難問。
中学受験生もステップを踏んで考えられるように、小問を加えます。
一緒に考えていきましょう。
(1)
Pを3で割り切れる整数、Qを3で割ると1あまる整数、Rを3で割ると2あまる整数とします。
P×P、Q×Q、R×Rを3で割った余りはそれぞれいくつになりますか。
-----
P×Pについては易しいはずです。
Pは3の倍数ですから、P×Pも3の倍数。したがって3で割った余りは0ですね。
では、Q×Qはどうでしょうか。
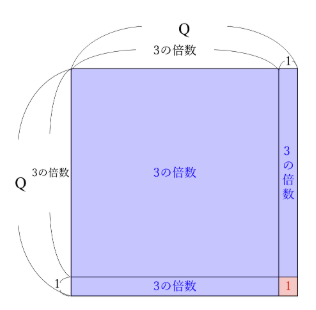
Qは3で割ると1あまる整数なので、Q×Qは上の図で示した正方形の面積と考えることができます。
ここで、図の青い部分は3の倍数になっているので、この正方形の面積を3で割ったときの余りは、右下の赤い部分、つまり1であることが分かります。
同じように3で割ると2あまる整数をRとしたときは、
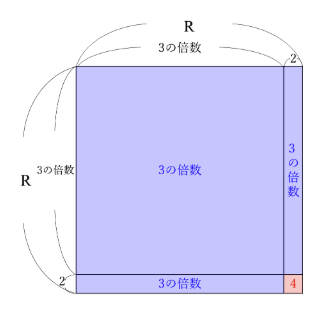
こんな図で表すことができ、これを3で割った余りは、右下の部分の4を3で割った余り、すなわち1になります。
まとめると、
3で割り切れる整数をPとすると、P×Pを3で割った余りは0、
3で割ると1あまる整数をQとすると、Q×Qを3で割った余りは1、
3で割ると2あまる整数をRとすると、R×Rを3で割った余りは1、
と分かりました。
(2)
A、B、Cを0より大きな整数としたとき、
9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
という式について、以下の文の空欄に当てはまる数を求めなさい。
9×A×Aを3で割ったときの余りは( ① )です。
B×B×B×B×B×Bを3で割ったときの余りは、
Bが3で割り切れる整数のとき( ② )、
Bが3で割ると1あまる整数のとき( ③ )、
Bが3で割ると2あまる整数のとき( ④ )です。
C×C×C×Cを3で割ったときの余りは、
Cが3で割り切れる整数のとき( ⑤ )、
Cが3で割ると1あまる整数のとき( ⑥ )、
Cが3で割ると2あまる整数のとき( ⑦ )です。
したがって、Bを3で割ったときの余りは( ⑧ )、Cを3で割ったときの余りは( ⑨ )です。
-----
9×A×Aは明らかに3で割り切れます。したがって、①は0です。
B×B×B×B×B×Bについて、
Bが3で割り切れる整数であれば、B×B×B×B×B×Bも明らかに3で割り切れます。したがって、②も0。
Bが3で割り切れないときは、 (1)で見たように余りの部分のみに注目すれば、積を3で割ったときの余りも分かります。
③は、余りの1に注目し、1×1×1×1×1×1=1を3で割ったときの余り、すなわち1です。
④は、余りの2に注目し、2×2×2×2×2×2=64を3で割ったときの余り、すなわち1です。
同じように考えれば、C×C×C×Cについても、3で割ったときの余りは、
Cが3で割り切れる整数のとき0…⑤、
Cが3で割ると1あまる整数のとき1…⑥、
Cが3で割ると2あまる整数のとき1…⑦
であることが分かります。
以上のことをまとめると、B×B×B×B×B×BもC×C×C×Cも、
BやCが3の倍数であれば3で割り切れ、BやCが3の倍数でなければ3で割ると1あまるということになります。
さて、そこで、
9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
という式について、少し考えてみましょう。
左側の9×A×Aは3の倍数です。
右側にあるB×B×B×B×B×BもC×C×C×Cも、3の倍数であるか、または3で割ると1あまる整数です。
これらを足し合わせて3の倍数になるのは、B×B×B×B×B×BとC×C×C×Cの両方とも3の倍数である場合しかあり得ません。
つまり、BもCも3の倍数であり、空欄の⑧と⑨に当てはまる数はいずれも0です。
-----
ここまでをまとめると、
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができるとき、「BもCも3の倍数である」ということが分かりました。
これを踏まえて、あと2ステップ考えてみましょう。
(3)
以下の文の空欄に当てはまる、最も大きい整数を答えなさい。
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができるとき、
(2)より、B×B×B×B×B×Bは必ず( ① )の倍数であり、C×C×C×Cは必ず( ② )の倍数です。
(4)
0より大きい3つの整数A、B、Cを使って、
N=9×A×A=B×B×B×B×B×B+C×C×C×C
と表すことができる整数Nのうち、最も小さいものを求めなさい。
-----
「BもCも3の倍数である」ということをヒントに、(3)(4)を考えてみてください。
ずいぶん長くなったので、今回はいったんここまで。
次回、解決編をお送りします。