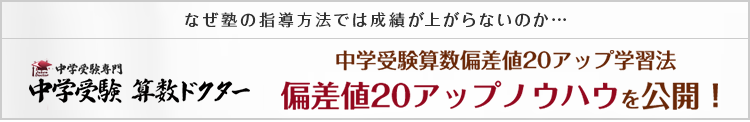みなさん、こんにちは。受験Dr.の亀井章三です。
今回はマルイチ算についてです。
受験算数をよく知らないと、マルイチ算って何?という反応になりそうですが、
数学で習う「一次方程式(文字式)」のことです。
文章題を計算式にするときに方程式を使えると、計算回数も少なく確実に
正解を出すことができます。そこで今回はマルイチ算の使い方を説明します。
マルイチ算の基本
求めたいものをマルイチ、つまり①とおきます。
1を整数倍すると、〇の中の数字が変化します。
1×2=②、②×3=⑥ という具合です。
注意しないといけないのは、②×③=⑥ではないということです。
同じ記号(〇どうし)は足したり引いたりすることができます
1+②=③ 、 ⑦-②=⑤ です。
それではマルイチ算について考えていきましょう。
マルイチ算の最終形は、=B という形になります。
これは=①×A なので、①×A=B ⇒ ①=B÷A となります。
〇の中の数字で割ると①が求められる、と覚えましょう。
「移項」を使いこなす
それでは、③-5=4 という式、①はいくらになるでしょう?
これは、③=5+4=9 になることは分かりやすいので、
1=9÷3=3 と求まります。
では、19-④=11 という式では①はいくらになるでしょう?
これも④=19-11=8 になることは分かりやすいので、
1=8÷4=2 と求まります。
それでは、30-③=④-12 はどうでしょう?
こうなると頭の中で整理するのが難しく、簡単には解けません。
そこで「移項」を使います。
移項とは、数字と正負の記号をセットにして、=の左から右、または右から
左へと移すことです。この時、+はーに、―は+に変わります。
例えば、
⑨+4=22 の場合、「+4」がセットになってます。
+を-にして「-4」にし、左から右へと移します。
⑨=22(-4) → ⑨=22-4=18 ①=18÷9=2
このルールは、〇のついた割合にも当てはまります。
先程の計算を見てみましょう。
30-③=④-12
まず、左右どちら側に「数字」、「割合」をそろえるかを決めます。
今回は左に「数字」、右に「割合」を集めます。
その場合、「-③」を右に、「-12」を左に移します。
30(+12)=④(+3)
42=⑦ ①=42÷7=6
もう1問練習してみましょう。
⑩+36=100-⑥
今回は割合を左に、数字を右にそろえます。
「+36」は「-36」に変えて右へ、「-⑥」は「+⑥」に変えて左へ移します。
⑩(+⑥)=100(-36)
⑯=64 ①=64÷16=4
移項自体は、単純なルールですのでおぼえてしまうととても便利ですし、中学に
進んでからも役立つでしょう。そして、このマルイチ算を使いこなすためには、文章題
の文章を数式に置き換えるという技術も必要になります。この「式にする技術」に
ついては次回お話したいと思います。