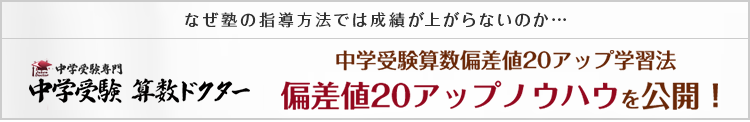こんにちは。
受験Dr.算数科講師の千葉 誠と申します。
今回は中学受験算数でおさえておきたい「分数の性質」を3つ紹介します。
それぞれに練習問題を用意してありますので解いてみてください。
1.「分数の大小」
分子が大きくなると大きい分数になり、分母が大きくなると小さい分数になる
![]()
![]() =A÷Bのように、分数はわり算の商を意味するので、「わられる数」である分子が大きくなると商は大きくなり、「わる数」である分母が大きくなると商は小さくなります。
=A÷Bのように、分数はわり算の商を意味するので、「わられる数」である分子が大きくなると商は大きくなり、「わる数」である分母が大きくなると商は小さくなります。
【問題】
![]()
【解説】
分子を30でそろえると、
![]()
Aは90より小さく78より大きい整数なので、A=79
2.「既約分数(それ以上約分できない分数)」
分子が、分母が共通の素因数を持たないとき、その分数は既約分数である
(例)![]() について、分子を素因数分解すると154=2×7×11。分母の195は2、7、11の倍数ではないので、
について、分子を素因数分解すると154=2×7×11。分母の195は2、7、11の倍数ではないので、![]() は既約分数。
は既約分数。
分母と分子が大きい分数では、小さい数から順に約分できるかどうかを確かめていくのは大変なので、素因数分解を利用すると既約分数を判別しやすくやります。
【問題】
分母が63で1以下の分数のうち、既約分数は何個ありますか。
【解説】
分母が63で1以下の分数は、![]() から
から![]() までの63個
までの63個
63=3×3×7より、既約分数となるのは分子が3か7の倍数でないとき
3の倍数は、63÷3=21(個)
7の倍数は、63÷7=9(個)
3と7の公倍数は、63÷21=3(個)
よって、既約分数でない(約分できる)ものは
21+9-3=27(個)
既約分数は、63-27=36(個)
3.「小数で表せる分数」
ある既約分数の分母の素因数が2か5だけのとき、その分数は有限小数で表せる
(円周率3.141592…のように小数点以下に数字が無限に続く小数を無限小数、無限に続かない少数を有限小数という)
(例)![]() について、分母の125を素因数分解すると、125=5×5×5。素因数が5だけなので、
について、分母の125を素因数分解すると、125=5×5×5。素因数が5だけなので、![]() は有限小数で表せて、
は有限小数で表せて、![]() =0.216となる。
=0.216となる。
![]() などは簡単に
などは簡単に![]() と表せることがわかると思います。
と表せることがわかると思います。
これはつまり分母が10×10×・・・×10の形で表せる分数は有限小数で表せることを意味します。
![]()
このように、分母の素因数が2か5だけのときは、2と5が同じ個数になるように変形することで分母を10×10×・・・×10の形に表すことができるため、有限小数で表すことができます。
【問題】
![]() が有限小数で表せるとき、Aにあてはまる最も小さい整数はいくつですか。
が有限小数で表せるとき、Aにあてはまる最も小さい整数はいくつですか。
【解説】
420を素因数分解すると、420=2×2×3×5×7
Aと約分することで2と5以外の3と7を消せば有限小数で表せるので
A=3×7=21
分数の性質は中学入試全体で見ると出題頻度は高くないですが、大学付属校を中心に頻出される学校がいくつかあります。
志望校で頻出の場合は今回紹介した性質と問題の解法を必ず身に付けておきましょう。
それでは、失礼します。