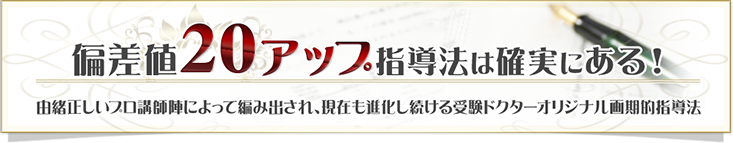みなさん、こんにちは。
受験Dr.社会科担当の松田吉郎と申します。
今回は、都道府県の名前を題材としたクイズにチャレンジしながら、地名をおぼえるという学習の本質に迫っていきたいと思います。
親子でどこまで正解に近づけるか、競争してみても面白いかもしれません。ぜひ、楽しみながら解いてみてください。
注意事項
・はじめは地図など見ずに考えてみましょう。
・時間制限は特に設けず、おまかせします。
・47都道府県の知識を問う純粋な問題なので、
なぞなぞのようなひねりはありません。
問題
問1『山』という漢字が使われている都道府県を6つすべて答えなさい。
(島・埼・岐のような部分的なものではなく、『山』という漢字が単体で使われている)
問2漢字で書きあらわしたとき、〇〇〇県になるものを3つすべて答えなさい。
問3ひらがなで書きあらわしたとき、『ほっかいどう』のように濁点がつく都道府県がいくつあるか答えなさい。
解答
問1 山形県・山梨県・富山県・和歌山県・岡山県・山口県
問2 神奈川県・和歌山県・鹿児島県
問3 20こ(北海道をふくめて)
出題の意図
4~6年生のお子さんの授業を担当したときのよくあるひとコマ。
松田「都道府県はおぼえたかな?」
生徒「完璧です!!」
松田「では、この問題は解けるかな?」
生徒「地図を見ないとわかりません…」
松田「信濃川はどこにあるでしょう?」
生徒「わかりません…」
松田「河口は新潟県にあるから地図で探してごらん。」
生徒「新潟県ってどこ?なに地方ですか?」
「地図を指して都道府県が答えられればOK!」という状態を完璧と言うお子さんは多いと思いますが、この状態にとどまったまま学習を進めると、上記の例のようにつまずきながらの学習になってしまい、全体として理解のスピードや精度が不安定なものになりやすいです。
入試問題では上記のようなクイズ形式で出題されることはほぼありませんが、アタマの中に作った地図の活用(インプットとアウトプット)を繰り返しながら付随する知識を増やしていくという学習は受験勉強で力をつけていくためにも重要であり、ひいては試験でのアタマの使い方にも通じるはずです。
本日のテーマでの具体的な目標は、47都道府県を地方別に確認することになります。
次の問題を解きながら都道府県名を地方別にチェックしてみてください。
練習問題 地方ごとに都道府県の数を答えなさい。
・北海道地方 →
・東北地方 →
・関東地方 →
・中部地方 →
・近畿地方 →
・中国地方 →
・四国地方 →
・九州地方 →
解答(上から)
1・6・7・9・7・5・4・8
よし、おぼえられた!…と思ったそこのあなたは、最後にマボロシの問4にチャレンジしてみましょう。
さっきよりすらすら解き進められたという手ごたえをつかんでいただければうれしいです。
問4 『島』という漢字が使われている都道府県を5つすべて答えなさい。
解答
福島県・島根県・広島県・徳島県・鹿児島県
まとめ
①問題を解いたあとなどに、「これを知っていれば解ける」という根本知識まで確認しましょう。
②「知っていてよかった・勉強した甲斐があった」という感覚を大事にしてモチベーションを高めましょう。
③ときには、みんなで楽しみながら学習する時間を作れるとよいでしょう。
お子さんの成績が伸びるサイクルに入る時には、これまで勉強してきたことが役に立ったという経験が原動力になっていると感じます。実際の現場でも、アタマを使って答えを導きだせたときの達成感に満ち溢れた表情を見ることが何より喜ばしいことだと思いながら、私自身も日々の授業を楽しむ気持ちで臨んでいます。
長くなりましたが、ここまでお読みいただいてありがとうございます。
社会科担当の松田吉郎でした。