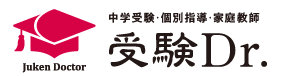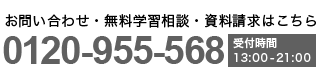東京成徳大学中学校説明会レポート(2025年2月26日)

本日は東京成徳大学中学校説明会を、受験Dr.久米 光太郎がご紹介いたします。
中高一貫部と高校からの入学生は敷地が別であり、500mはなれたところにそれぞれ校舎があります。
学校からのアピールポイントは、①Appleの認定校になっている②卒業生に対する国公立・早慶上理・GMARCHの合格者の割合が20%、③土台となる学力を養う教え型の授業と、進むべき道を切り拓くための学び型の授業を行っている➃中2全員がフィリピンのセブ島に行き、中3の希望者がニュージーランドに行くことで生徒たちがいろんなことを体験し視野が広がる。
■ アクセス
・地下鉄南北線「王子神谷駅」下車、2番出口より徒歩5分
・JR京浜東北線「東十条駅」下車、徒歩15分
2025年4月25日に行われた東京成徳大学中学校の入試報告会の内容をまとめました。
この内容についてのご質問は、受験Dr.までお願いします。
プログラム
東京成徳の教育概要・入試結果
中高一貫部副校長の石井英樹先生より東京成徳の教育概要と入試結果についてのお話がありました。
その中から一部を紹介いたします。
その中から一部を紹介いたします。
入試結果と東京成徳の教育概要について
近年受験者が増えてきた。第一志望の人に入ってほしいので2/1の倍率は抑えた。後半の日程は倍率が若干上がった。
第一志望優先入試を行った。第1回の合格最低点は全体の45%にしたが、他の回は50%程度。
中高一貫部と高校は混ざらない。授業は別に行う。団体の部活や文化祭などの行事は一緒。
来年本校は創立100周年を迎える。東京成徳の成徳とは「徳を成す」こと。「誰とでも温かく接することができる」という意味。
先進的な学び→ICTが目的ではない。ツールを使いこなすのが当たり前。必要な時に効率よく使えるようにしていきたい。
グローバル→子どもたち将来大人になった時に日本語しか使わないということは考えにくい。いろんな人たちと触れ合いながらツールとして英語を学んでいければいい。
自律した学習者→我々が教えこんでいくのは限界がある。自ら走っていく学習者を育てたい。
創造性→本校はAppleの認定校であり、常にアップデートを図っている。創造性を項目に分けて考えている。独自性・発想力、デザイン開発、探究心・批判力など。主体性、チャレンジ精神を意識しながら授業デザインを行っている。
教え方やグループ学習はあくまでも手段。目標は自律した学習者になること。
第一志望優先入試を行った。第1回の合格最低点は全体の45%にしたが、他の回は50%程度。
中高一貫部と高校は混ざらない。授業は別に行う。団体の部活や文化祭などの行事は一緒。
来年本校は創立100周年を迎える。東京成徳の成徳とは「徳を成す」こと。「誰とでも温かく接することができる」という意味。
先進的な学び→ICTが目的ではない。ツールを使いこなすのが当たり前。必要な時に効率よく使えるようにしていきたい。
グローバル→子どもたち将来大人になった時に日本語しか使わないということは考えにくい。いろんな人たちと触れ合いながらツールとして英語を学んでいければいい。
自律した学習者→我々が教えこんでいくのは限界がある。自ら走っていく学習者を育てたい。
創造性→本校はAppleの認定校であり、常にアップデートを図っている。創造性を項目に分けて考えている。独自性・発想力、デザイン開発、探究心・批判力など。主体性、チャレンジ精神を意識しながら授業デザインを行っている。
教え方やグループ学習はあくまでも手段。目標は自律した学習者になること。
6年間のプログラムについて
中高一貫部教頭・入試広報部部長の和田一将先生より、6年間のプログラムについてのお話がありました。
6年間のプログラム
近年のご家庭は自分の子に合う学校を模索している。本校は2017年からiPadを使っており、Appleが国際的に認定する数少ない学校の1つ。いろんなことに挑戦して結果を残している学校が認定される。日本では他に三田国際と湘南学園がある。認定を受けていると、いろんな国の学校が授業で取り組んでいる様子が分かる。この前はヒジャブをつけたムスリムの子たちが学校に来た。本校ではiPadを使ったイキイキした授業をしている先生が多くいる。探究のためには学びの基礎が必要。教え型と学び型の両輪を回す。ついていけない子への補習を行っている。
W担任制を取っており、自分は英語だが、理系の先生に入ってもらって理系の生徒のための小論文の指導をしてもらった。中1ギャップを埋めるため、中1にスケジュール表を渡してスケジュール管理の手助けをしている。
本校は二者面談、三者面談が多い。成績データ、アンケートでコンピテンシーを分析して性格的なタイプを分けて、あなたはこういう性格だからこうした方がいいという形で面談を行っている。
高大連携でのプログラムの授業ではコードやアプリを作るところまでいく。
世界を知るために、全員が中2でフィリピンのセブ島に2週間行く。中3でニュージーランドに行くのは希望制。
中1英語と数学は分級して8クラス編成で細かく見ている。英検の練習をネイティブの先生とやる、オンライン英会話やAIとの英会話をするなどの補習を行っている。AIは生徒それぞれのレベルに合わせられるのがいい。中2は全員がフィリピンに語学留学をする。コロナで外に出られなかった子たちが親元を離れて出ていくことが大きい、GLCという施設で朝から英語学習を行い週末は海に行ったりスラムに行って交流したりする。いろんな世界があるんだということを見てほしいと思っている。日本人の人が経営している孤児院ではネグレクトにあったり人身売買を止められてここにいる子たちがいる。食事なども寄付で成り立っている、そういう子たちと交流する。費用は2週間で30〜40万円とリーズナブル。
中3で行うニュージーランド3ヶ月間の留学は選択制。人種と民族がポイント留学ではどの地域を選ぶのかが重要。一つの教室に白人も黒人もポリネシア系の人もいるという環境が魅力。セブ島やニュージーランドに行ったことで高校で本気で留学したいというご家庭も増えている。
自分を拓くための探究の授業、高1でゼミをやる。好きなことを深く学ぶ。先生が前年から企画を立て、選択する生徒が少ない講座は取りやめになるので先生も本気で頑張る。鯵を釣ってマイクロプラスティックを探す、コーヒーを1年間たて続けるなどのゼミがある。ゲームをひたすら作り続けるゼミでは上手くいかない経験が多くなる。そういうところから学ぶ。医療ゼミは豚の解剖、薬剤師体験をする。いろんなゼミがある。
高2では実地踏査型修学旅行を行い、それぞれにテーマを決めて1年間かけて論文を書く。引用のやり方、仮説の立て方を学ぶ。探究学習の怜として、川の歴史が街の歴史にどういう影響を与えるのかを考え道頓堀を調査した生徒がいた。
進路の幅が広がっていった。目的があるから進路を選ぶという形に変わっていった。海外に進路をとる子たちも増えてきた、英語の検定と学校の成績で推薦を取れる海外大学推薦制度が使える学校が50校ある。TOEFLの対策や奨学金の取り方などをサポートする。「未来を見据え、世界を知る、自分を拓く」のが本校の教育コンセプト。
W担任制を取っており、自分は英語だが、理系の先生に入ってもらって理系の生徒のための小論文の指導をしてもらった。中1ギャップを埋めるため、中1にスケジュール表を渡してスケジュール管理の手助けをしている。
本校は二者面談、三者面談が多い。成績データ、アンケートでコンピテンシーを分析して性格的なタイプを分けて、あなたはこういう性格だからこうした方がいいという形で面談を行っている。
高大連携でのプログラムの授業ではコードやアプリを作るところまでいく。
世界を知るために、全員が中2でフィリピンのセブ島に2週間行く。中3でニュージーランドに行くのは希望制。
中1英語と数学は分級して8クラス編成で細かく見ている。英検の練習をネイティブの先生とやる、オンライン英会話やAIとの英会話をするなどの補習を行っている。AIは生徒それぞれのレベルに合わせられるのがいい。中2は全員がフィリピンに語学留学をする。コロナで外に出られなかった子たちが親元を離れて出ていくことが大きい、GLCという施設で朝から英語学習を行い週末は海に行ったりスラムに行って交流したりする。いろんな世界があるんだということを見てほしいと思っている。日本人の人が経営している孤児院ではネグレクトにあったり人身売買を止められてここにいる子たちがいる。食事なども寄付で成り立っている、そういう子たちと交流する。費用は2週間で30〜40万円とリーズナブル。
中3で行うニュージーランド3ヶ月間の留学は選択制。人種と民族がポイント留学ではどの地域を選ぶのかが重要。一つの教室に白人も黒人もポリネシア系の人もいるという環境が魅力。セブ島やニュージーランドに行ったことで高校で本気で留学したいというご家庭も増えている。
自分を拓くための探究の授業、高1でゼミをやる。好きなことを深く学ぶ。先生が前年から企画を立て、選択する生徒が少ない講座は取りやめになるので先生も本気で頑張る。鯵を釣ってマイクロプラスティックを探す、コーヒーを1年間たて続けるなどのゼミがある。ゲームをひたすら作り続けるゼミでは上手くいかない経験が多くなる。そういうところから学ぶ。医療ゼミは豚の解剖、薬剤師体験をする。いろんなゼミがある。
高2では実地踏査型修学旅行を行い、それぞれにテーマを決めて1年間かけて論文を書く。引用のやり方、仮説の立て方を学ぶ。探究学習の怜として、川の歴史が街の歴史にどういう影響を与えるのかを考え道頓堀を調査した生徒がいた。
進路の幅が広がっていった。目的があるから進路を選ぶという形に変わっていった。海外に進路をとる子たちも増えてきた、英語の検定と学校の成績で推薦を取れる海外大学推薦制度が使える学校が50校ある。TOEFLの対策や奨学金の取り方などをサポートする。「未来を見据え、世界を知る、自分を拓く」のが本校の教育コンセプト。
社会科の授業実践
中高一貫部社会科主任の中川琢雄先生より社会科の授業実践についてお話がありました。
そのなかから一部を抜粋して紹介します。
そのなかから一部を抜粋して紹介します。
社会科の授業実践
今日は①社会科の学びを通じてお子さんがどう成長しているか、②社会科で何を学ぶのか、③成長を促す6年間の授業デザインについてお話しする。
チャレンジ精神・創造性・主体性を持つ自律した学習者をどうやって育てていくか。社会科の学びは暗記という子どもも保護者も多いが、社会科の学びはもっと豊かなもの。ロシア・ウクライナ戦争について考えるとすると、この戦争はどうやって始まったか、どうやって終わるのかを考えられるのが社会。この戦争の歴史的要因を考えるのが歴史的・時間的アプローチ、世界に与える影響(例えばアフリカの小麦が上がったこと)などを考えるのが地理的・空間的アプローチ、このような戦争を防ぐにはどうすればいいかを考えるのが公民的・制度的アプローチ。
学び方を学ぶのがグループワーク授業。授業を通じて人間関係を作って欲しい。自分の考えを相手に伝えるスキルを学んで欲しい。コミュニケーションの仕方について子どもたちがいろいろ考える。この子の意見に反対の時、どうやって怒られないで伝えることができるかを自分で考える。「世界の古代文明に共通する点はあるのだろうか」というグループワークを行ったとき、先生は答えを教えずに自分で調べる。自分たちで文明の要素を書き出し年代別に区分けして発表したグループがあって感動した。1年後の「江戸幕府の成立→鎖国までの流れ」のグループワークでは、自分たちで考えて色分けした表を1時間で作った。キリスト教を追放することに成功した、と彼らがまとめた。まとめる分類するというスキルが身についてきた。「縄文と弥生の違い」ではビジュアルで絵で表現した。稲作・身分・戦争などの違いについて自分で優先順位をつけることをやった。「日本のかさね」ではiPadでシンプルに色を重ねて表現することをやった。「侘び寂びを写真で表現しよう」では写真を撮って解説をつけた。
中学生では学び方を学ぶ、高校は自ら学ぶ。「御成敗式目を評価する」では、法典としての御成敗式目を現代と比べて評価した。
AIを使いこなせるようになるため、AIでさまざまな人物を作成し、その人物に対するインタビューを作成することもやった。足利尊氏を作成しインタビューしたときの映像を紹介する。
これで学力つくんですか?という疑問があるのはもっとも。去年の6年生は江戸時代の幕末の分岐点を自分たちで発表するということをやった。これは問いを自分たちで作るという文科省の指導要領に合致する。時代の転換や現代の日本の課題について考えられるようになる。東大の歴史の問題を改題して定期テストで出したけれど生徒たちは6割取ってくる。この授業で力がついたと思いますかのアンケートを取ったら、「はい」が70%、「どちらかと言えばはい」が30% 。自分も自信がついた生徒たちは自分で学んでいる。
チャレンジ精神・創造性・主体性を持つ自律した学習者をどうやって育てていくか。社会科の学びは暗記という子どもも保護者も多いが、社会科の学びはもっと豊かなもの。ロシア・ウクライナ戦争について考えるとすると、この戦争はどうやって始まったか、どうやって終わるのかを考えられるのが社会。この戦争の歴史的要因を考えるのが歴史的・時間的アプローチ、世界に与える影響(例えばアフリカの小麦が上がったこと)などを考えるのが地理的・空間的アプローチ、このような戦争を防ぐにはどうすればいいかを考えるのが公民的・制度的アプローチ。
学び方を学ぶのがグループワーク授業。授業を通じて人間関係を作って欲しい。自分の考えを相手に伝えるスキルを学んで欲しい。コミュニケーションの仕方について子どもたちがいろいろ考える。この子の意見に反対の時、どうやって怒られないで伝えることができるかを自分で考える。「世界の古代文明に共通する点はあるのだろうか」というグループワークを行ったとき、先生は答えを教えずに自分で調べる。自分たちで文明の要素を書き出し年代別に区分けして発表したグループがあって感動した。1年後の「江戸幕府の成立→鎖国までの流れ」のグループワークでは、自分たちで考えて色分けした表を1時間で作った。キリスト教を追放することに成功した、と彼らがまとめた。まとめる分類するというスキルが身についてきた。「縄文と弥生の違い」ではビジュアルで絵で表現した。稲作・身分・戦争などの違いについて自分で優先順位をつけることをやった。「日本のかさね」ではiPadでシンプルに色を重ねて表現することをやった。「侘び寂びを写真で表現しよう」では写真を撮って解説をつけた。
中学生では学び方を学ぶ、高校は自ら学ぶ。「御成敗式目を評価する」では、法典としての御成敗式目を現代と比べて評価した。
AIを使いこなせるようになるため、AIでさまざまな人物を作成し、その人物に対するインタビューを作成することもやった。足利尊氏を作成しインタビューしたときの映像を紹介する。
これで学力つくんですか?という疑問があるのはもっとも。去年の6年生は江戸時代の幕末の分岐点を自分たちで発表するということをやった。これは問いを自分たちで作るという文科省の指導要領に合致する。時代の転換や現代の日本の課題について考えられるようになる。東大の歴史の問題を改題して定期テストで出したけれど生徒たちは6割取ってくる。この授業で力がついたと思いますかのアンケートを取ったら、「はい」が70%、「どちらかと言えばはい」が30% 。自分も自信がついた生徒たちは自分で学んでいる。
2026年度入試に向けて
中高一貫部教頭・入試広報部部長の和田一将先生より、2026年度入試に向けたお話がありました。
その中から一部を紹介いたします。
その中から一部を紹介いたします。
2026年度入試に向けて
昨年2025年度から第一志望優先入試を行った。2/1が受けやすい。成徳が大好きな子たちになるべく入ってきて欲しい。成徳好きな子をきちっと囲っていきたい。
来年度の変更点は2/4の入試日程追加。事故的に落ちてしまう子がいるので2/4に2科も4科も入試をやる。試験日に保護者向けの説明会をやる。
卒業生に対する国公立・早慶上理・GMARCHの合格者の割合が20%。人気がない時期があったので卒業生の人数は今後数年間減っていくが、成徳大好きな子たちに入ってきてもらっているので、合格者の割合は減らない。
生徒たちは魚釣りをしてそれを捌いて食べる経験をする、大泣きする女の子もいる。生徒は経験から学ぶ、経験に優るものはない。
東京外語大に入った子の卒業生インタビュー、ニュージーランド留学で日本の良さを認識、文化祭でLGBTグッズを販売、LGBTについて考えたくて大学を選んだ。
生徒は自分で考え自分の納得する進路を選ぶ。日本ではやりたいことができないから海外に行った子もいる。私たちの学校には多様性を育む土台がある。
来年度の変更点は2/4の入試日程追加。事故的に落ちてしまう子がいるので2/4に2科も4科も入試をやる。試験日に保護者向けの説明会をやる。
卒業生に対する国公立・早慶上理・GMARCHの合格者の割合が20%。人気がない時期があったので卒業生の人数は今後数年間減っていくが、成徳大好きな子たちに入ってきてもらっているので、合格者の割合は減らない。
生徒たちは魚釣りをしてそれを捌いて食べる経験をする、大泣きする女の子もいる。生徒は経験から学ぶ、経験に優るものはない。
東京外語大に入った子の卒業生インタビュー、ニュージーランド留学で日本の良さを認識、文化祭でLGBTグッズを販売、LGBTについて考えたくて大学を選んだ。
生徒は自分で考え自分の納得する進路を選ぶ。日本ではやりたいことができないから海外に行った子もいる。私たちの学校には多様性を育む土台がある。
学校訪問を終えて
探求型の学びとその実践については説得力がありました。中高一貫部(昨年度の卒業生77名)と
高入生(昨年度の卒業生407名)は混ざらず、別の敷地で別の授業が受けられる点は魅力だと感じました。
高入生(昨年度の卒業生407名)は混ざらず、別の敷地で別の授業が受けられる点は魅力だと感じました。