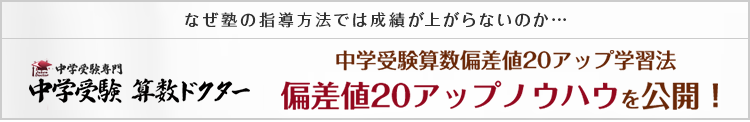こんにちは。
受験Dr.の吉野です。
「復習テストでは点数がとれるのに、実力テストになると点数が取れない」 「実力テストは受ける意味があるのか?」 そういったお悩みの声をよく聞きます。
今回は、試験範囲が決まってない実力テストに対してどう取り組めば良いか? 「実力テストの活用方法」についてお答えしていきます。
1 実力テストの位置づけ
試験範囲の決まっている復習テストは、日ごろからコツコツと学習を継続できているかどうかを確認するためのテストです。したがって、点数(理解度)が重要になります。では、試験範囲の決まっていない実力テストはどんな意味があるのでしょうか。ずばり、「弱点のあぶり出し」です。
実力テストは復習テストと違って、点数は重要ではありません。もちろん点数が取れた方がいいですが、それよりも重要なことは、現段階で何ができて何ができていないのか、自分の立ち位置を確認することです。実力テストの結果をしっかり分析して、どのように学習を進めるか、どの単元を復習すべきか、自分なりの課題を作っていきましょう。そして、次の実力テストまでにこれらの課題が克服できるように取り組んでいきましょう。
以下は、この「弱点のあぶり出し」とその「対処方法」についていくつかのパターンに分けて説明します。
2 現状の分析
実力テストからわかる弱点と言っても、いろいろな場合があります。まずは、最近の模試の結果からお子様の状況が、以下の4つのどのパターンに該当するか分析しましょう。もちろん、複数のパターンに該当する場合もあります。
(1) 暗記系、一行問題などが取れていない。
(2) 家での解きなおしでは正解できるのにテストではできない。
(3) 正答率の高い問題を極端に落としている。
(4) 正答率が高い問題はできても、正答率の低い問題はできない。
3 パターン別の対処方法
(1) 暗記系、行問題などが取れていない。・・・「基礎学力不足」
基礎学力が定着していないと思われます。授業中は集中して聞いていますか?授業の復習や宿題をしていますか?家庭学習の量は足りていますか?日ごろの自分の学習スタイルを見直しましょう。
【対処方法】 復習は、習ってから48時間以内に実施する。
基礎力不足の最大の要因は、学習したことを忘れてしまうことにあります。
「エビングハウスの忘却曲線」をご存じでしょうか?人は一度学習した内容を覚えているつもりでも、時間が経つと記憶が薄れていきます。ドイツの心理学者のエビングハウスによると、1日後には34%、2日後には27%しか覚えていないという研究結果があり、記憶を残すためには反復して復習することが効果的と言われています。しかも、ある程度記憶が残っているうちに覚えなおしをすれば、それほど時間をかけずに記憶を定着させることができます。理想的には、学習した日から48時間以内に復習を行うことです。すると効果的に記憶を残すことができます。
(2) 家での解きなおしでは正解できるのにテストではできない。・・・「メンタルの問題」
試験会場でライバルが周囲にいる独特な雰囲気の中で、緊張してしまう。早く解かなければというプレッシャーがかかる。わからない問題にあたって、パニックになる、などです。実力があってもそれが発揮できていない状態です。
【対処方法】 家庭学習は、時間を測って実施する。
プレッシャーに弱いお子様は、日ごろから時間を気にしない学習をしている傾向にあります。家庭学習ではテキストを終わらせることを優先していませんか?「時間内に解く」という意識をもって家庭学習に取り組むように変えましょう。まずは、テキストを終わらせるのにかかった時間を計測します。実施していくうちにかかる時間がだいたいわかってきます。次に、少しでも早く終わらせるように終了時間を設定して目標時間内に解ききること目指します。常に時間を意識した家庭学習を行いましょう。
(3) 正答率の高い問題を極端に落としている。・・・「ケアレスミス」
基礎学力不足もありますが、それ以上にケアレスミスを疑ってください。ケアレスミスの最も効果的な解決法は、「見直し」です。日ごろから見直すことを意識しましょう。ここでは「見直し」以外のケアレスミス対策をご紹介します。
【対処方法】 問題文をしっかり読み、印をつける。
問題文をよく読まずに解くお子様が意外に多くいます。塾のテキストが例題⇒類題の問題構成のため、問題文をよく読まなくてもテキストの問題は解けてしまいます。この調子でテストの問題もちらっと見ただけで、「テキストの問題を同じように解けばいい」と勝手に判断すると条件が違っていたりしたことに気づけない場合があります。例えば、四分円が2つ組み合わせたラグビーボールのような図形の問題で、面積を求める練習を沢山やったので面積を求める問題だと勝手に判断してしまったが、実はまわりの長さを求める問題だった、という話を生徒から聞いたことがあります。問題文は最後まで丁寧に読んで、何を問われているのか、何を答えるのかを意識して、大切なことろに印をつけながら問題文を読みましょう。
(4) 正答率が高い問題はできても、正答率の低い問題はできない。・・・「根本原理の理解不足」
一番多いパターンです。易しい問題は取れるが、応用問題になると解けない原因は、テキストの解き方や解答を丸暗記しているからです。テキストと同じ問題なら解けるけどひねられると途端にできなくなるお子様は、実力がないというよりも根本原理・注目ポイントがわかっていない方が多いです。
【対処方法】 根本原理を理解するためにプロの力を頼りましょう。
単元ごとに問題を解くためのポイント=根本原理が必ずあります。テキストに根本原理が書いてある場合も多いですが、その重要性を意識せずに飛ばし読みをしたり、完全に理解しないまま、公式だけ暗記したりしているお子様が多いです。応用問題ではこの根本原理が大切で、何に注目すれば良いのかのヒントになります。勘の良いお子様は、多くの問題を解いているうちになんとなく根本原理がわかってくる方もいます。しかし自分で気づけない場合や短期間で結果を求める場合は、家庭教師や個別指導のプロの講師に頼った方が確実です。
今回はここまで。実力テストの結果を分析して、有効に活用できることを期待しています。
では、また次回でお会いしましょう。
受験Dr.吉野でした。